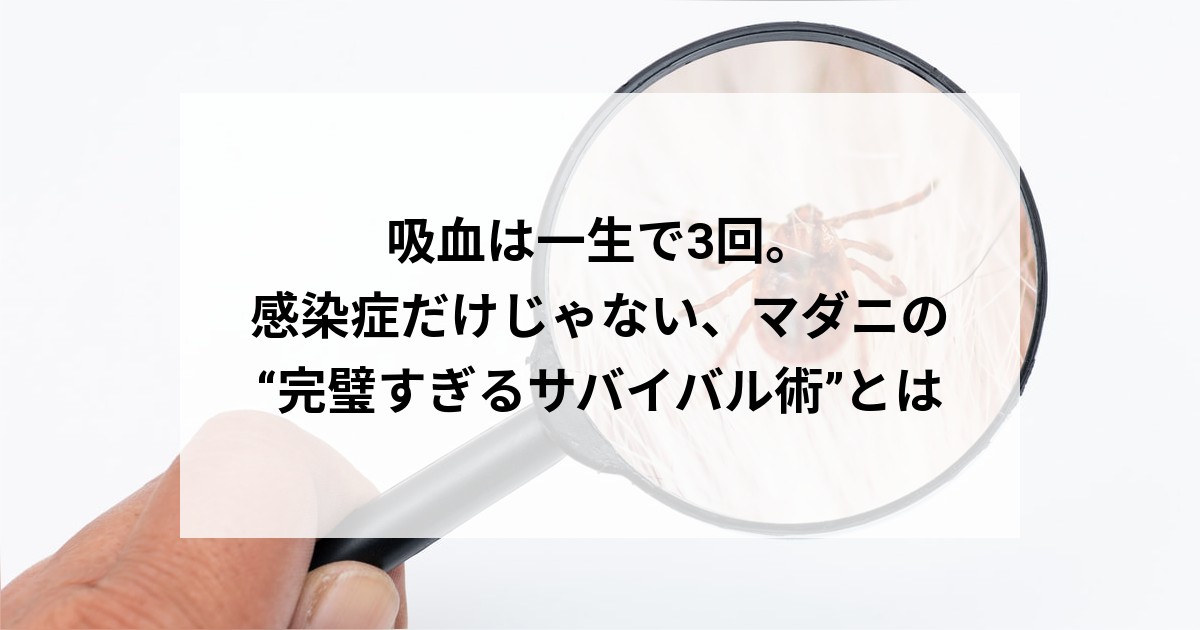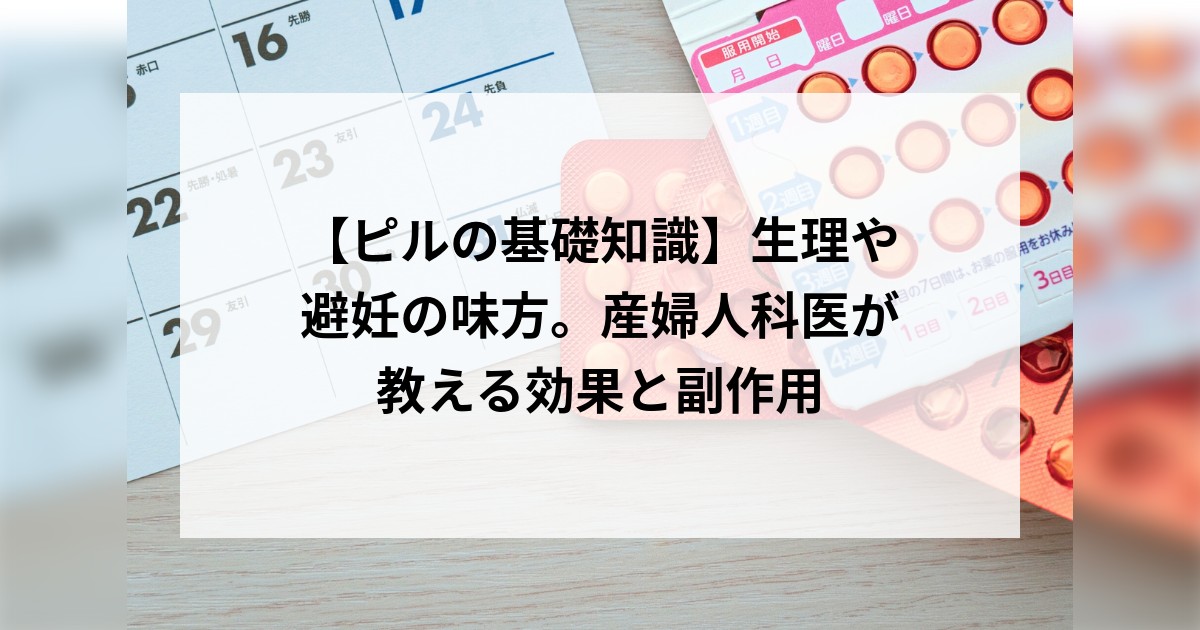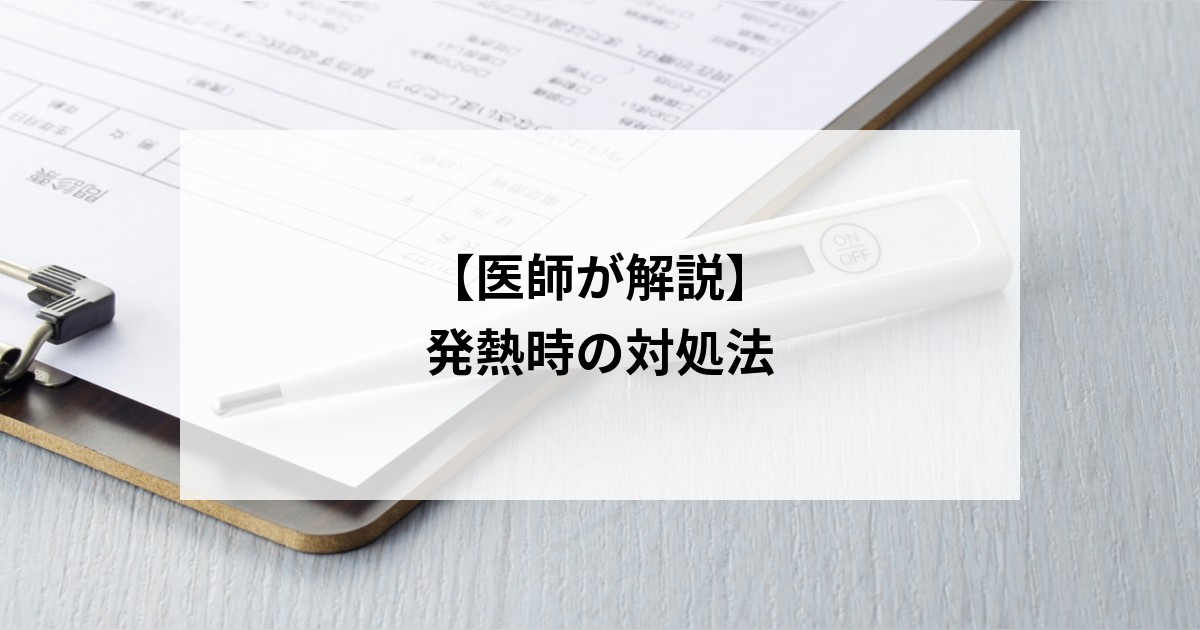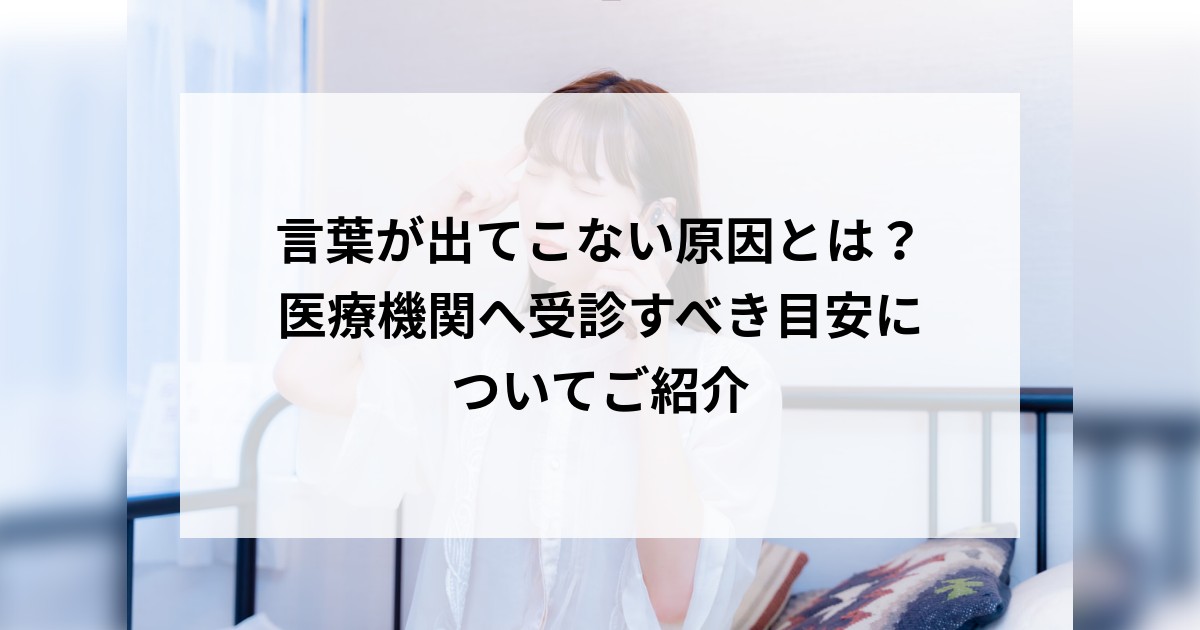※本記事にはマダニの写真が掲載されています。苦手な方はご注意ください。
夏が近づくと話題になる「マダニ」。
草むらや登山道で注意が呼びかけられる、体長数ミリ程度の小さな吸血生物です。SFTS(重症熱性血小板減少症候群)などの重い感染症を媒介することから、新聞やニュースで見聞きした方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回はそんなマダニについて、「感染症の専門家」関根先生にお話を聞いてきました。
感染症だけが注目されがちですが、マダニという生物の驚くべき生態と、私たちの想像をはるかに超える不気味な魅力をお楽しみください。
今回お話をお伺いした人
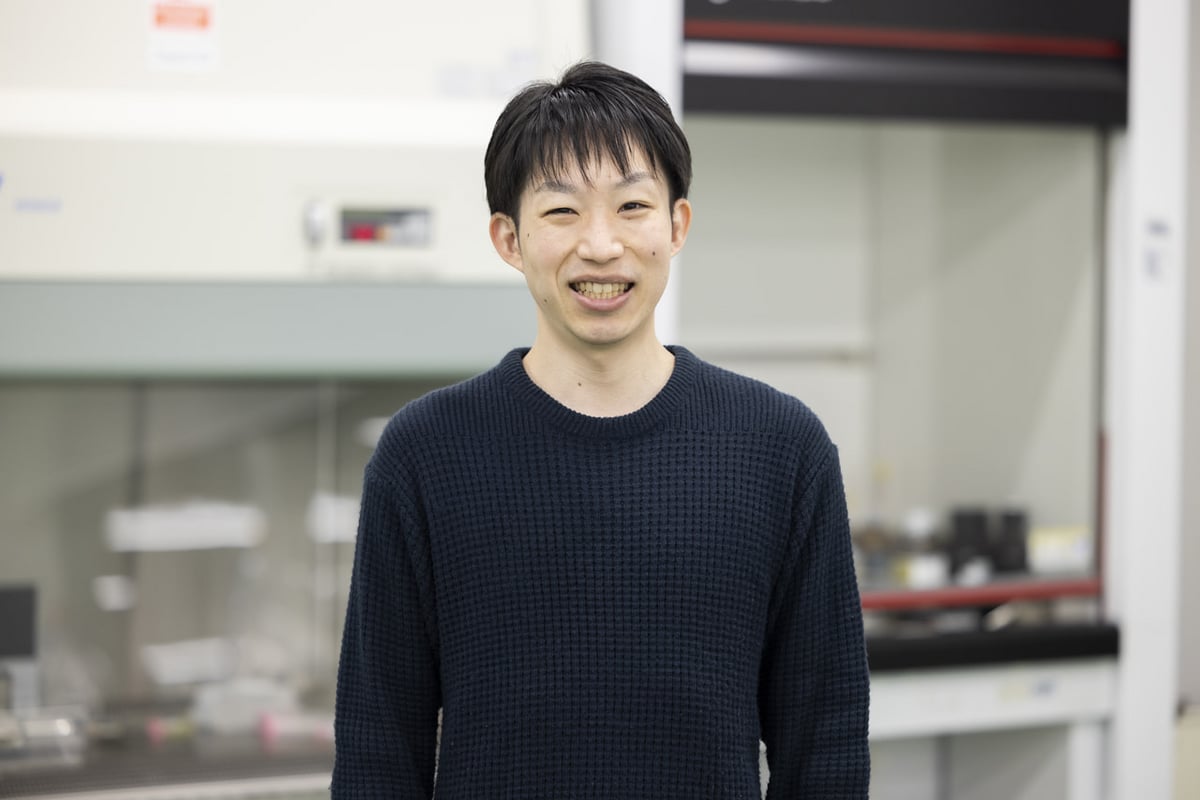 森ノ宮医療大学 医療技術学部 臨床検査学科 准教授/臨床検査技師 関根 将 先生
森ノ宮医療大学 医療技術学部 臨床検査学科 准教授/臨床検査技師 関根 将 先生
京都大学大学院 医学研究科人間健康科学系 修士課程修了(人間健康科学)後、大阪公立大学大学院 医学研究科 博士課程修了(医学)。専門は寄生虫学、 ウイルス学など。臨床検査技師として京都第二赤十字病院に勤務、2019年4月に着任、2025年より現職。寄生虫感染者を減らすため、ケニアで現地調査を行うこともある。
一生に3回しか血を吸わない!?
マダニはクモの仲間(※)で、世界中で約1,000種類が確認されており、日本には約50種類が生息しています。
すべてが吸血性ですが、人の血を吸うのはその中でも約10種類に限られ、牛や鳥など種類によって好みがあります。
ある研究者が、牛の血を好むダニの進路上に手を差し出したところ、そのまま手のひらの上を通過されたこともあるのだとか。
※足は8本ですが、若い時は6本しかないんですって
とくに驚くのは、マダニは一生でたった3回しか吸血しないという事実。
“幼ダニ”と“若ダニ”のときに、脱皮にむけてエネルギーを蓄えるため1回ずつ、 “成ダニ”になって産卵のために3回目の食事を行います。絶食にも強く、1〜2年も血を吸わずに生きていけるというから驚きです。
次項ではそんなマダニの食事をご紹介します。
 吸血するマダニ
吸血するマダニ
恐竜時代から続く“吸血特化型”のからだ
マダニの体は、まさに吸血に特化したつくり。
8本ある足のうち、頭側の2本にある「ハーラー器官」と呼ばれるセンサーで動物の体温や呼気を察知することができ、この“両手”を広げて獲物を待ち構えます。
 こんな感じ…?
こんな感じ…?
特に特徴的なのが、頭部の構造。マダニの頭部には口しかなく、目は(退化して無い種類がほとんどですが)背中にあり、呼吸はお尻で行います。
吸血の瞬間には頭を獲物の皮膚に差し込み、セメントのように固める物質でガッチリ固定。長ければ1週間程度かけて血を吸います。
また吸血中は、血を固めさせない・血管を拡張する作用を持つ特殊な唾液を分泌します。
この成分は本来マダニが持っていなかったものですが、ある研究によると、はるか昔に恐竜から吸血した際に遺伝子の水平伝播(※)により得た可能性があるんだそう。
吸血した生物の特徴を自分のものにできるなんて、驚きですよね。
さらにマダニの唾液腺にはα-Galという成分が含まれており、これが体内に入ることで“牛肉アレルギー”になるケースも報告されています。
※吸血した生物の遺伝子情報を受け継ぐこと
 (左)吸血後 (右)吸血前
(左)吸血後 (右)吸血前
【関連記事】寄生虫や虫刺されの仕組みをもっと知りたい方はこちらもおすすめ!
【実は役立つ!?】寄生虫のフシギにせまる
【かゆーい!やられた!!】いやーな虫刺され。蚊の知られざる生態!
まさにパンドラの箱?マダニによる感染症
マダニが媒介する感染症として代表的な「重症熱性血小板減少症候群(以下、SFTS)」は、致死率が30%にのぼり、発熱・頭痛・吐き気などインフルエンザに似た症状に加え、血小板減少や多臓器不全へと進行することもある危険なウイルス性感染症です。
2024年に抗ウイルス薬「アビガン」が認可(保険適用)されたため、今後は致死率が下がることが期待されています。
ところでこのSFTSは、2011年に世界で初めて報告(※)された非常に新しい病気です。
しかし驚くべきことに後に行われた調査で、2005年に原因不明で亡くなった方の検体からも、当時はまだ知られていなかったSFTSへの感染が確認されました。
※日本では2013年に初症例
また遺伝子解析が進んだ近年、マダニの体内から新種のウイルスが次々と発見されています。マダニは、まだ知られていない病気を秘めている可能性があるのです。
意外と身近なマダニのリスク
キャンプや登山、庭いじりなど野外活動を行う際はマダニ対策をしましょう。
・肌の露出を控える服装
・虫よけスプレー(ディートやイカリジン配合)を使う
→おすすめは「ディート30%」のものだそう

万が一刺されても自分で取り除かず、病院を受診するのが基本です。
無理に取ろうとするとマダニの頭部が皮膚に残ったり、指でつまんだ際に(まるでスポイトのように)マダニの体液が体内に入り込んだりする可能性があります。
どうしても病院に行けない場合は、市販されているマダニ除去器具を用いたり、それも無い場合はできるだけ頭部に近いところから捻るように慎重に取り除きましょう。
また、「草むらに入らなければ大丈夫」と思っているあなた。ペットを介して人に移るケースもあります。
とくに猫はマダニに好まれやすく、犬に比べて感染リスクが高いという報告も。
まれにですが人から人への感染(血液や体液を介してと考えられていますが、はっきりとは分かっていません)が確認された例もあります。
まとめ
いかがだったでしょうか。
マダニは、人間にとっては感染症の媒体になったりアレルギーを引き起こしたりと、困った存在であるのは間違いありませんが、その生態には不思議な魅力があったのでは。
実は今回、マダニ感染症をテーマに記事を書こうと関根先生に取材したのですが、途中からマダニに関するさまざまなトリビアが飛び出し、それが面白くて急遽マダニそのものにフォーカスした内容に変更しました。
マダニについて楽しそうに話す関根先生に影響されたのか、筆者もいつの間にかマダニのことを「この子」と呼んでいることに気づくシーンも…。
とはいえ刺されると困ることには違いないので、今後も適度な距離感をとりつつ、付き合っていきたいと思います。
この記事はいかがでしたか?もっと知りたいこと、みなさんのマダニに関するエピソードなどがあればぜひ、Instagramのコメント欄で教えてください!たくさんのコメントをお待ちしています✨
セラピア | Instagram
【この記事を書いた人】
カツオ
三度の飯より釣りが好き。三度の飯は麺が好き。な元サッカー審判員(ギリギリ30代のアラフォー男)