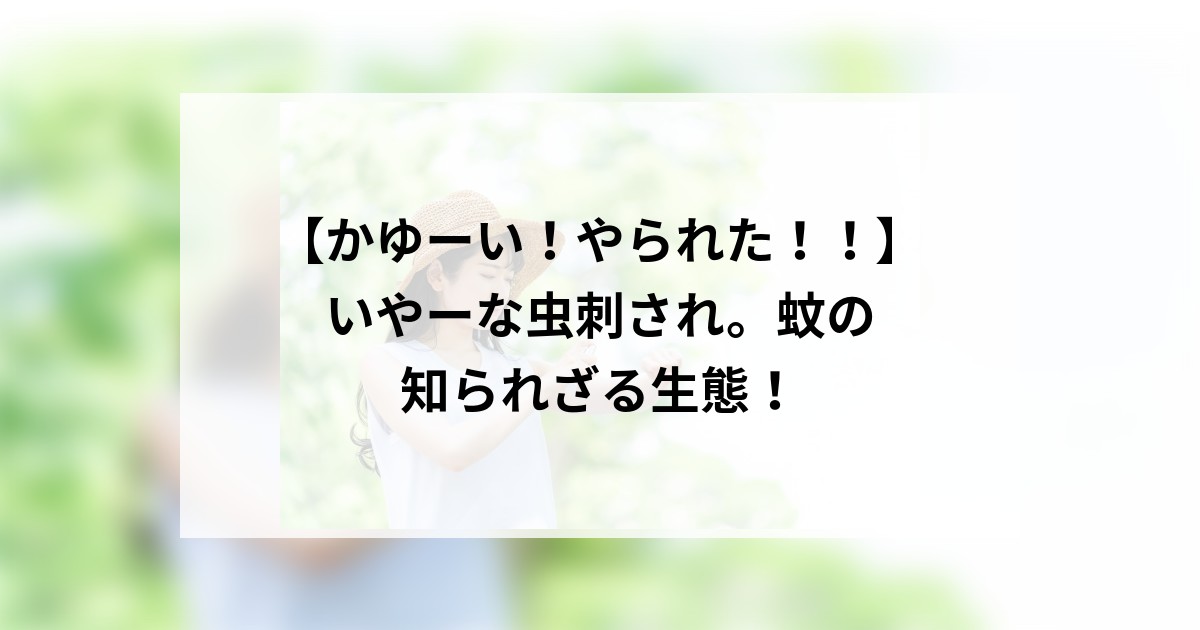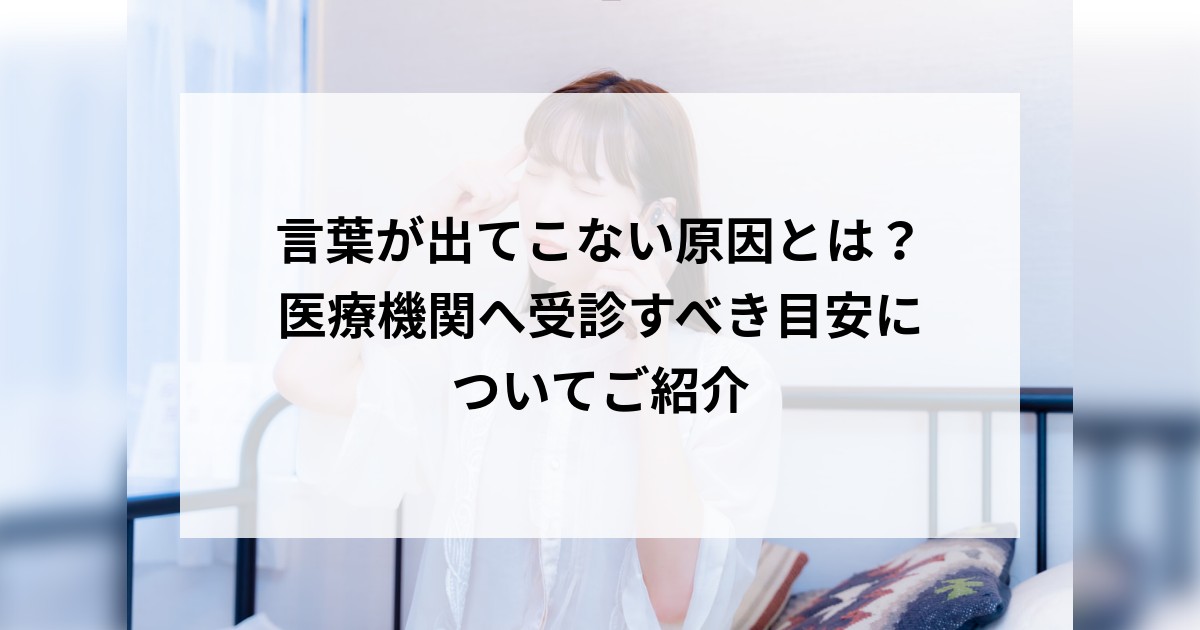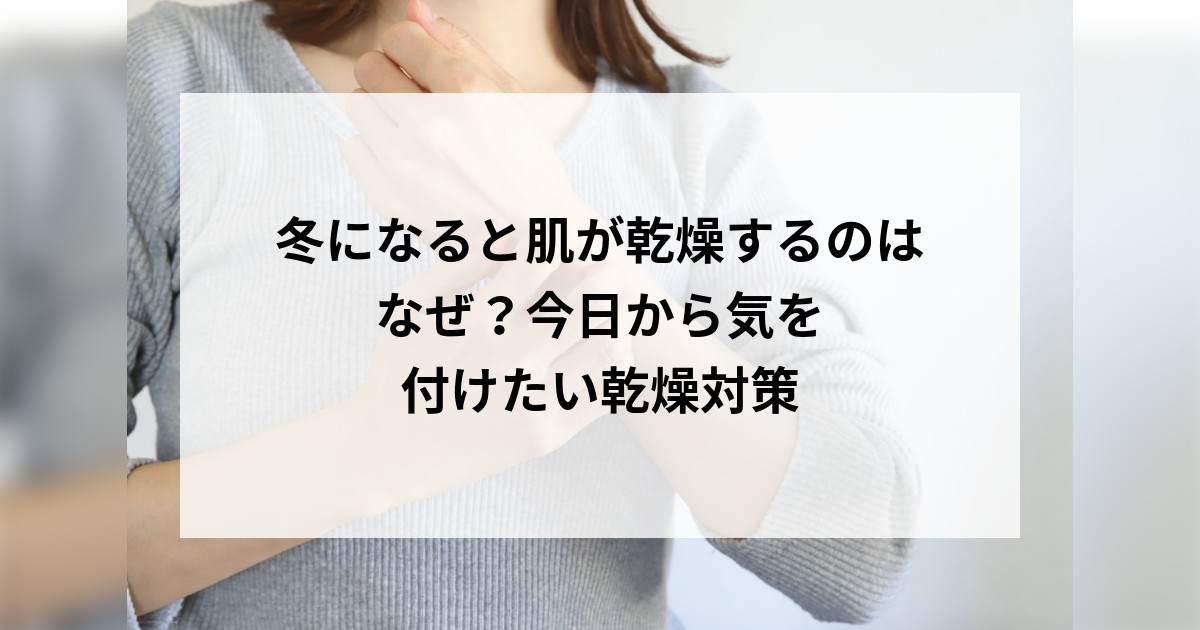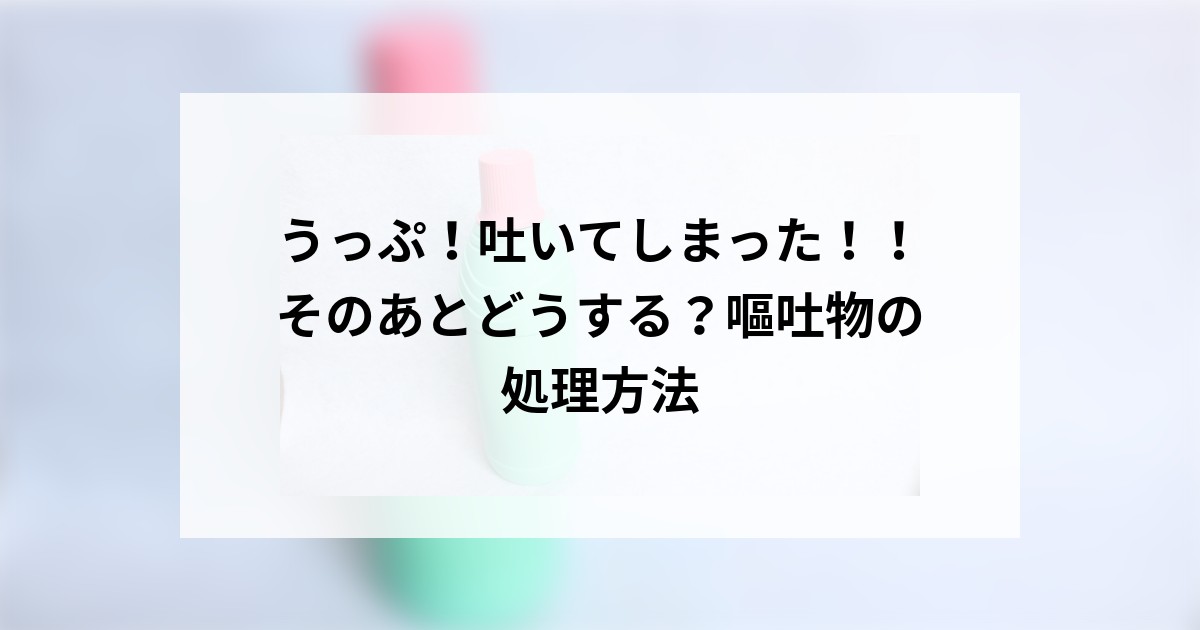暑中お見舞い申し上げます。山でキャンプをしたり、街でショッピングをしたり、勉強や仕事に勤しむ方もおられると思います。そんな誰もが遭遇する夏のアレ、そう「蚊」です。今回は興味深い生態から予防するポイントまで、知ると誰かに話したくなる情報をお届けします。
今回お話をお伺いした先生
森ノ宮医療大学 医療技術学部 臨床検査学科 准教授/臨床検査技師 関根将 先生
大阪公立大学大学院 医学研究科 博士課程修了(医学)。専門は寄生虫学。京都第二赤十字病院で臨床検査技師として勤務。2019年4月に本学に着任し、助教・講師を経て2025年4月より現職。

なぜ蚊はヒトを刺すのか?
蚊は普段、花の蜜を吸って生きています。しかし産卵前であるメスの蚊には優れたエネルギーが必要であるため、栄養補給としてヒトや動物の血液を吸います。そのためオスは血液を吸うことはありません。そして血液は大事な栄養源であることから、驚くことに蜜が入る胃袋とは別で血液用の胃袋を持っています。これぞまさしく別腹!(ちなみにオスの特徴としては、メスのフェロモンを察知するよう触角がフッサフサなことです。)
なお、血液を吸った蚊は体重がおよそ2倍に増すため、飛ぶスピードが著しく低下します。急に体が重くなることから一旦壁に止まる習性があり、壁で休憩したときに血液から不要な水分を捨てて、濃縮した栄養たっぷりの血液を体内に摂り込みます。
なぜ夏に蚊は多いのか?
蚊が羽化するのは、暖かい環境。日本には四季があるため、夏が近づく頃から蚊が活動し始めます。寒い時期に産卵されたものは、卵の状態で冬を越し、翌年の夏に成虫へと成長します。そういったわけで夏場に多く蚊に刺されることになります。蚊の寿命は成虫になってから1ヶ月程度。なんと蚊は1度交尾すると何度も産卵ができることから、血液を吸って卵を産む…を繰り返しており、成虫のあいだに3~4回程度は産卵を行っています。

蚊に刺されることで身体に出る反応
かゆくなったり、赤くなったりする原因は、刺されるときに蚊の唾液がヒトの体内に入り、それに対するアレルギー反応が現れるためです。 また、反応のあらわれ方がひと夏のあいだで変わるというから驚きです。
■4型アレルギー反応
別名、遅延型アレルギー反応とも。夏が到来して私たちが初めて蚊に刺されたときにはこの反応が起きます。刺されてから蚊が飛んでいき、しばらく経ってから「かゆい!」と感じるものです。
■1型アレルギー反応
別名、即時型アレルギー反応とも。1年のうち何回か蚊に刺されると、反応の出方が変化します。即時型になると刺された瞬間に「かゆい!」と感じます。反応速度が遅かったものが、俊敏にあらわれるようになります。
■無反応
短期間で何度も蚊に刺されすぎると無反応になり、かゆみを感じなくなります。これは耐性ができることによるもの。ただし期間が空くと耐性は薄れリセットされるため、翌年の夏には4型アレルギー反応で「かゆい!」を感じる体に戻っています。
アフリカ大陸のように1年を通して気温が高い環境では蚊が年中いるため、この地域に暮らす人たちは刺されすぎて無反応状態になっています。それゆえに蚊が媒介するマラリアの感染対策が進まない状況があるのです。
刺されたときは、かゆみ止めを塗る、冷やすなどの対処をしてください。なお、爪でバッテンにするのは、医学的なエビデンスはないようです。
刺されやすい条件、そして予防のポイント
蚊は汗のニオイに引き寄せられること、加えて黒っぽい色(濃い色)の服を着ている方が刺されやすいといわれています。そのため汗をかいたらこまめに拭く、明るい色の服を着用することが蚊を防ぐポイント。
虫よけスプレーは皮膚から気化する際、蚊が嫌がる成分が広がるようにできているため、服でなく肌にかけましょう。また、昔からある蚊取り線香は、除虫菊という植物由来の有効成分(ピレスロイド)が使用されているそうです。天然原料で安心ですね。
加えて、そもそも蚊を発生させない環境を作ることも大切です。蚊は水面に産卵をし、ボウフラ(幼虫)が発生します。そのため住まいの周りに水が溜まらないようにしておきましょう。
そして先述のとおり、蚊は血液を吸った後に壁に止まる習性があることから、壁にスプレーを施すことも非常に有効です。(壁に止まる時点では誰かが1度は吸われています…。)
最近の研究では、遺伝で刺されやすさが決まっていることがわかってきました。兄弟姉妹がいる場合1人は刺されやすく、もう1人は刺されにくいという傾向にあるそうです。面白い研究結果ですね。また男女差については、一般的に男性の方が女性より体温が高く、発汗量が多いため刺されやすいとされているものの決定的な証拠はありません。
蚊のあれこれ
■世界モスキートDay
8月20日は「世界モスキートDay」と定められています。これはロナルド・ロス氏がマラリアは蚊の媒介によって感染することを発見した日であるため。日本でマラリアは撲滅していますが、現在も世界では(特に乳幼児が)死に至ることもある感染症として知られています。
■注射針は蚊の針を模している
蚊に刺されても痛くないですよね。この構造を真似て医療用の注射針は作られています。医療に応用される技術とは、凄まじいですね。ちなみに蚊には5種類(上唇、下唇、メインの針、大顎2本、小顎2本)の計7本も針があるそう。小顎で皮膚を痛くないように切って、メインの針を刺し入れて…と精密機械のような動きをしています。このうち注射針に応用しているのはメインの針です。
まとめ
関根先生は研究のためケニアに赴かれることがあります。暑い国で一年を通して蚊がいる環境にもかかわらず上述予防策のほか、日没が近くなると長袖を着用して肌の露出をなくす、蚊帳を用いる等の対策をされるため「蚊に刺されることはなかった」とおっしゃっていました(※1)。また虫よけスプレーは、有効成分ディートが30%含まれるものを使用されていたそうですよ(※2)。みなさんも予防を行い、「かゆい!」に悩まされない夏を過ごしましょう。
ちなみに関根先生は生きもの好きが高じて、寄生虫学を研究されるようになられました。休日には動物園、水族館に赴かれているそうですよ。
(※1)マラリア原虫を媒介するのはハマダラカという種類の蚊であり、これは夜間吸血性があるため。
(※2)日本国内で入手可能なディート最大濃度が30%。小学生以下は10%以下を使用することが推奨されています。
関根先生の他の記事はこちら

この記事についてのご感想やご質問があれば、ぜひInstagramのコメント欄で教えてください!みなさんのコメントをお待ちしています✨
【この記事を書いた人】
はくまい
美味しいごはん(とお酒)が大好き!ごはんのために働き、ごはんのために眠る!!今日もカロリーと幸せを噛みしめ、数字より気持ちで生きる30代おなご。