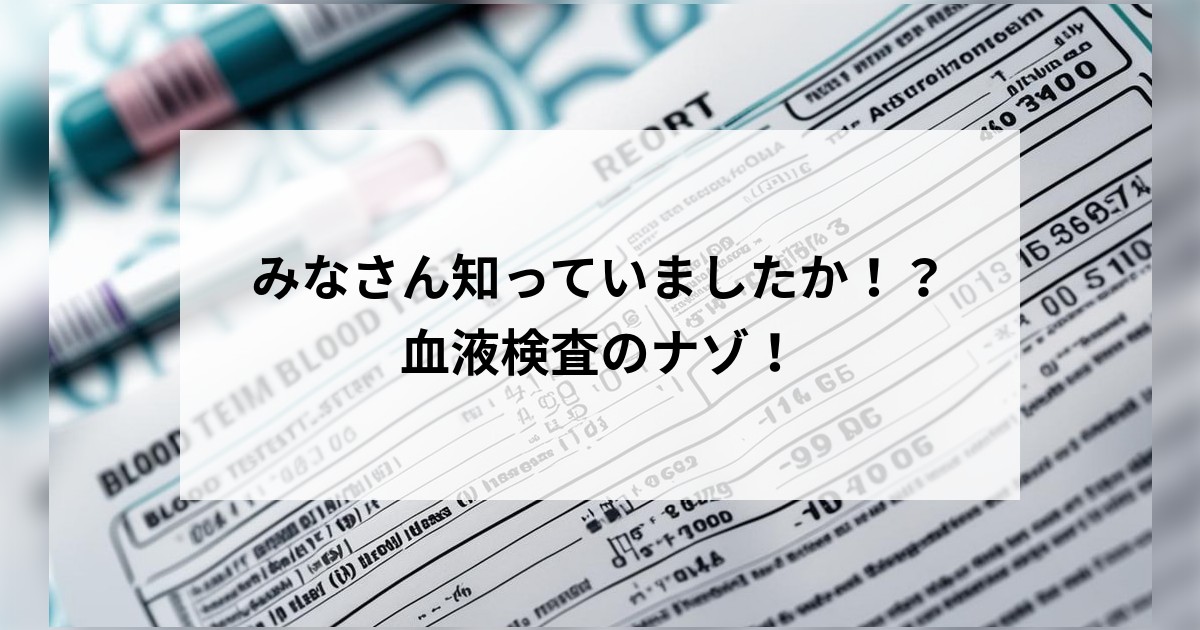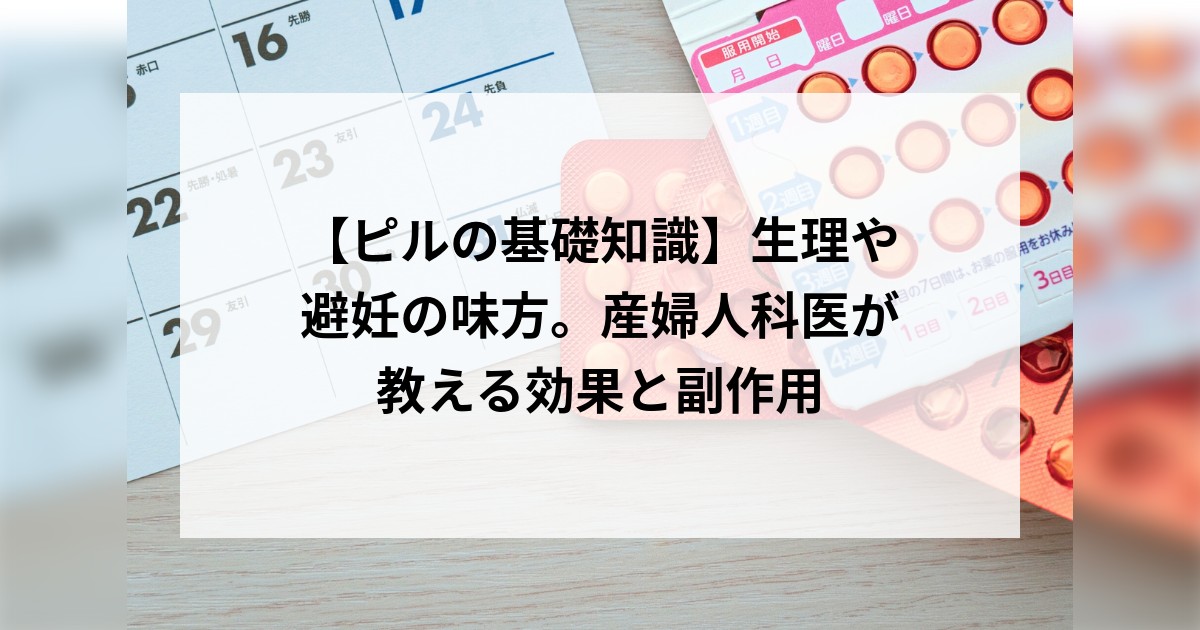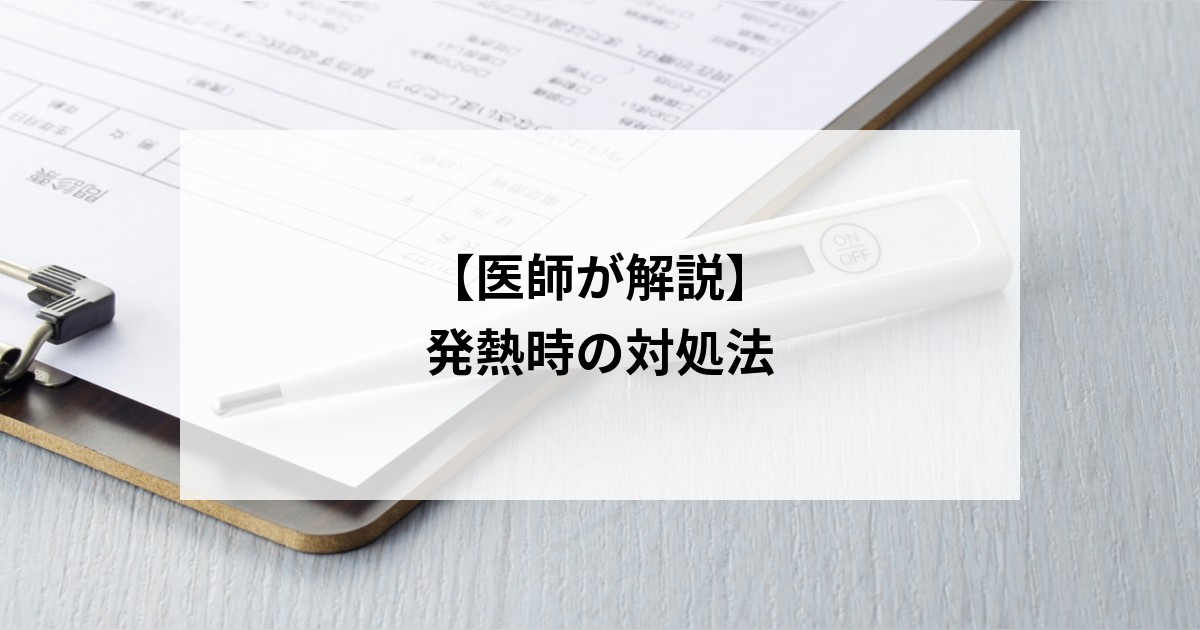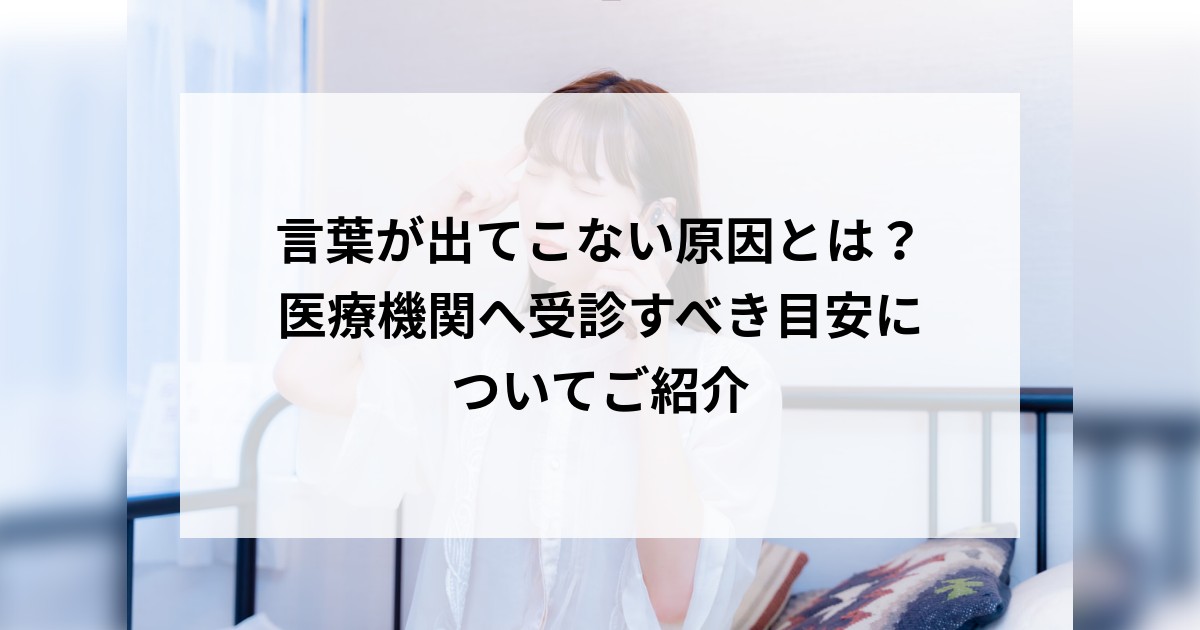健康診断や人間ドックなどの際に行う血液検査、採血をするときはドキドキしませんか?
みなさんこんにちは、毎回ドキドキしてしまう筆者です。
ところで受診時の様子を思い返すと「たくさん血を抜いたけど、こんなに必要なの?」、「なぜ分けて入れているの?」と考えたことがありませんか?
今回はそんな疑問を血液検査の専門家『臨床検査技師』の先生にお聞きしました。
ちなみに臨床検査技師ってどんなことをするの?という興味を持ってくれた方や人間ドックについて知りたい方は、下の記事も見てくださいね!!
【医療の仕事に迫る!】検査データを通じて患者さんを診る!臨床検査技師って?
【人間ドックのススメ】100 年時代を元気に生きるコツ
今回お話をお伺いした人

森ノ宮医療大学 医療技術学部 臨床検査学科 教授/臨床検査技師 藤原 牧子 先生
大阪市立大学大学院 医学研究科血液腫瘍制御学 博士後期課程修了、博士(医科学)。専門は血液検査学。臨床検査技師として大阪公立大学医学部附属病院中央臨床検査部に勤務、2016年4月に本学に着任し、講師・准教授を経て、2025年4月より現職。
こんなにあるの!?血液検査の種類と違い。
血液検査は、「検体検査(採取した血液や尿、便や細胞などを調べる検査のこと)」の一種で、血液に含まれる細胞・酵素・抗体などを数値化します。血液は生命の維持活動(私たちの健康)のために、欠かせない役割を担っています。血液検査を行うことで全身の健康状態を把握できることから、体の不調や病気を見つけることが可能です。また調べたい項目によって、検査の種類が変わります。
では血液検査の種類について、代表的なものをご紹介します。
〇血球計数検査…血液中の赤血球、白血球、血小板などの細胞成分を調べます。抗凝固剤という薬剤を入れた採血管に血液を入れて、貧血や多血症、感染症、白血病などの疾患や止血機能などを検査します。
〇血液生化学検査…遠心力で成分を分離させる遠心分離機にかけて、血液中における特定の物質を調べます。それにより肝臓や腎臓、心臓などの臓器が正常に機能しているかどうか、また糖尿病や脂質異常症といった病気に罹っている可能性があるかを検査します。
〇血液凝固検査…血液が固まる時間や凝固因子の量を測定し、出血を防ぐための機能が正常に働いているかを検査します。
〇免疫血清検査…感染症や自己免疫疾患、アレルギーなどの特定の疾患や免疫機能の異常などを検査します。
〇血液型検査…安全な輸血が行えるか、臓器移植の際に拒絶反応を抑えられるか、また妊娠の管理などのため血液型を調べます。赤血球表面の抗原が何かを調べる検査と、血漿中の抗体を調べる検査をします。
上記のように、それぞれの検査で異なる体の機能や病気の状態を測定し、結果を示すことができます。これだけ多くのことを様々な方法で知れるとは、驚きですね。
ちなみにこの検査を行っているのが臨床検査技師です。現在、検体採取は臨床検査技師の業務のなかで重要な位置づけとなっています。医療機関や研究所によって、使う機械や業務をどこまで担当するのかも大きく変わりますが、藤原先生が勤務されていた医療機関では、外来採血業務のほとんどを臨床検査技師が担当されていたため、患者さんの緊張を和らげ、良い状態の血液を採取することをとても大切にしていたとおっしゃっていました。

だから多くの血液が必要なのか。複数の採血管が必要な理由。
様々な種類の検査があることは理解いただけたかと思いますが、次は「そんなにたくさんの血液が必要なの?」また、「どうして採血管が複数用意されているの?」という疑問に迫りたいと思います。
実は検査方法によって私たちの血液は、全血(すべての成分が浮遊した状態の血液)で分析する場合と、血清(血液が凝固した時に、上澄みにできる液体成分)・血漿(赤血球、白血球、血小板などを除いた液体成分)だけを分析する場合があります。
また分析までの保存温度が凍結・冷蔵・室温など指定されているものや、血液が凝固するのを防ぐため採血管に添加されている薬剤が同じであっても、血液に対しての薬剤量に違いがあるなど、細かいきまりごとがあります。
検査に使う血液などの材料(検体)は採取された瞬間から変化し始めます。患者さんの体内の状態を正確なデータとして示すために、各検査に応じた最適な添加剤と保存条件が細かく決められています。そのため、同じ検体(この記事では血液)であっても検査ごとに分析方法が異なり、それに応じた量の血液が必要になります。結果として、複数の採血管に分けて保存する必要があります。
ちなみに採血のとき、血がスーッと自動的に採血管に吸い込まれていくのを見たことがありませんか。あれは採血管内部の圧力が外部の圧力よりも低い陰圧状態になっているために起こります。採血管に分けて入れる時間の短縮と、医療者の安全性(血液に直接触れないなど)の確保という点で最近の主流になっています。
適切に採取した検体を精度管理された機械や一定の手技で、より真値に近いデータとして報告することで臨床検査技師は質の高い医療の提供に貢献していると、藤原先生はおっしゃっていました。

最後に
血液検査は細かくルール付けされており、血液(検体)は良い状態で採取し、適した状態で保存しなくてはなりません。それゆえたくさんの血液を採らないといけないことがわかってもらえたのではないかと思います。高い精度が要求される検査ですが、臨床検査技師が正確な分析を行っていることで安心して受けることができ、精密な結果から病気の早期発見につながります。
知識を身につけたことで、筆者の注射に対するドキドキも少し和らぎそうです!
また藤原先生は「当たり前のように表示される数値や画像などのデータですが、検査をひたむきに行い、素早く医師に報告を繰り返し行っている医療者の存在を知ってほしい。今回は血液検査の紹介でしたが、本当に幅広い仕事が臨床検査技師にはあります。」とおっしゃっていました。
血液検査の基礎知識に加えて、臨床検査技師が高度かつ様々な専門知識と技術でみなさんの健康を支えていることも知ってもらえれば嬉しいです。
この記事についてのご感想やご質問があれば、ぜひInstagramのコメント欄で教えてください!みなさんのコメントをお待ちしています✨
【この記事を書いた人】
Θ(シータ)
Θに似ているたらこくちびるが由来。1歳の女の子パパをしています。