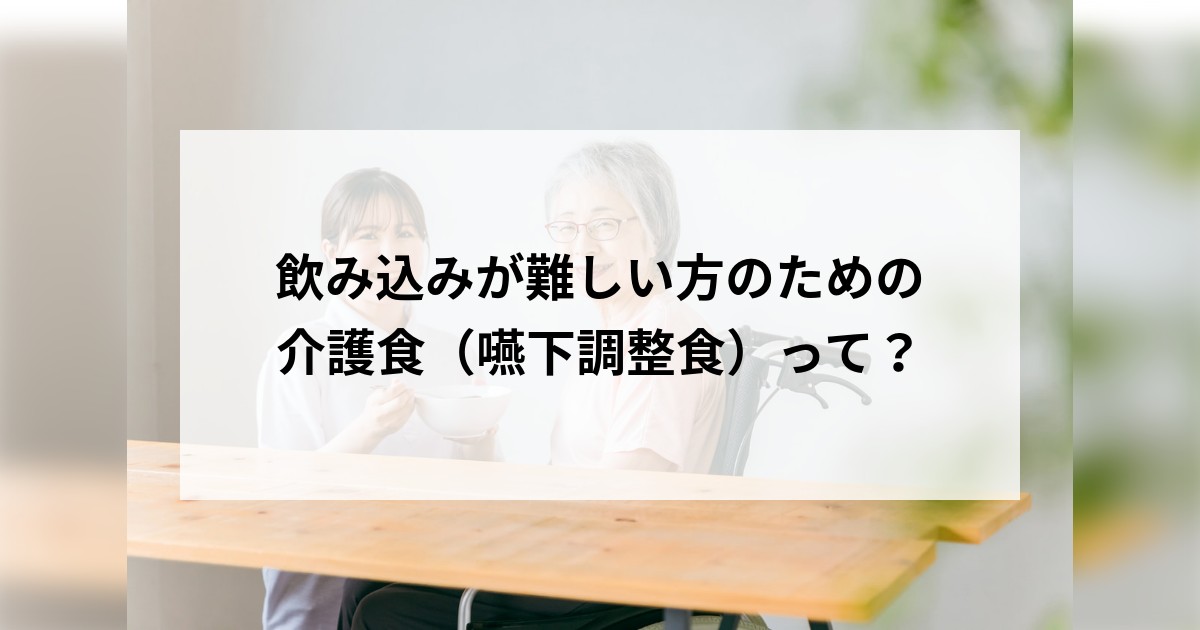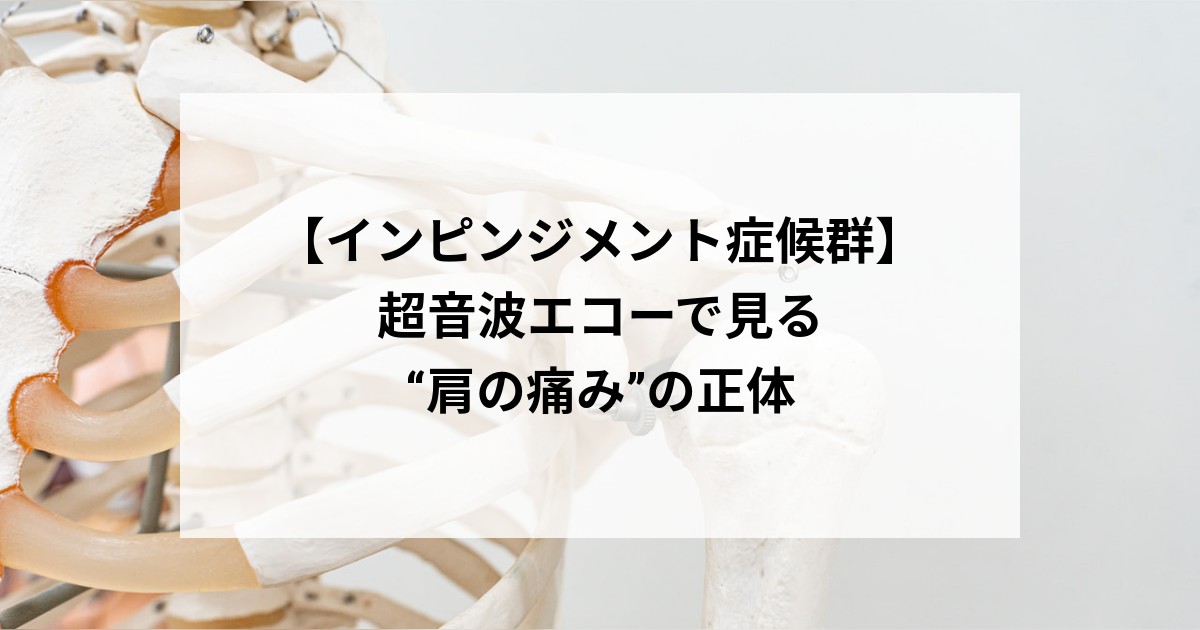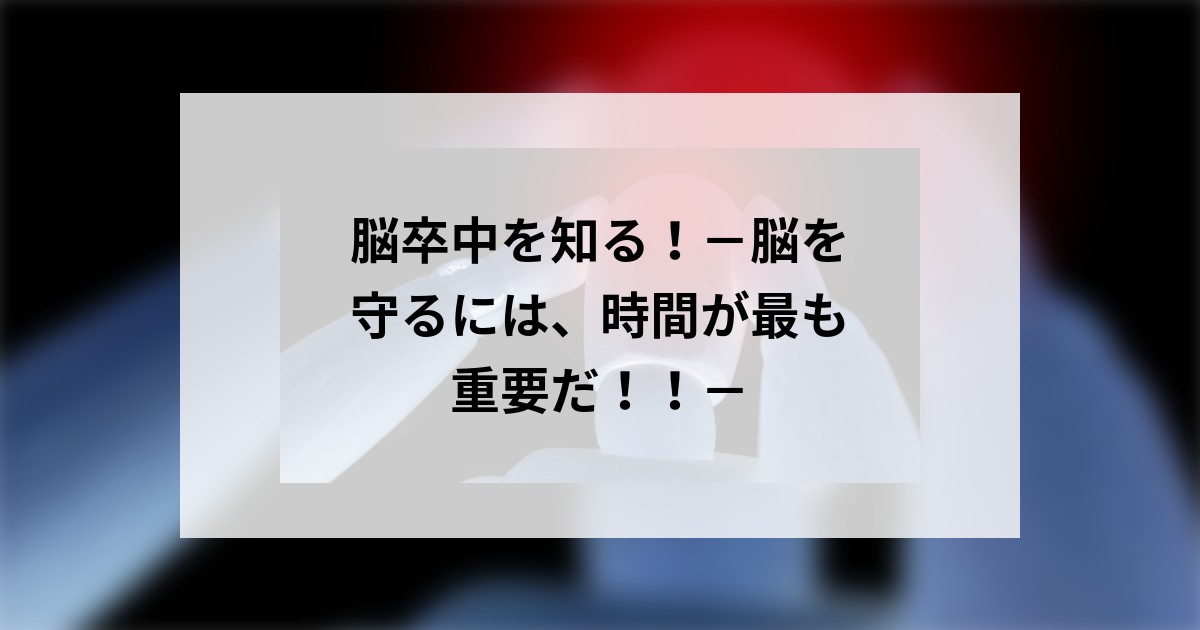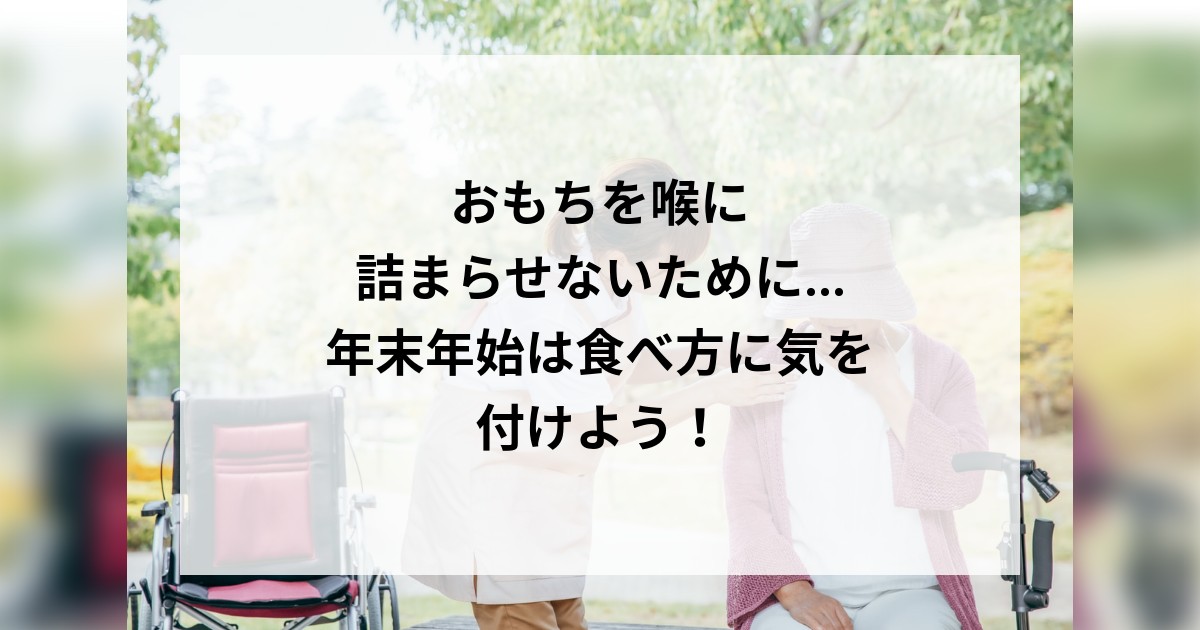「食べること」は人生の楽しみのひとつですが、病気や加齢に伴って食べる機能が低下してしまう方も多くいらっしゃいます。そんな方々のために日々研究、開発されているのが「嚥下調整食」、いわゆる「飲み込みが難しい方のための介護食」です。今回は、飲み込む機能が低下する理由や嚥下調整食の分類、近年ますます進化している嚥下調整食についてお伝えします!
今回お話をお聞きした人

森ノ宮医療大学 総合リハビリテーション学部 言語聴覚学科
准教授 南都 智紀 先生
広島県立保健福祉大学卒業後、県立広島大学総合研究科保健福祉学専攻 修士課程修了(修士)。大阪大学歯学研究科口腔科学専攻 博士課程修了(博士)。森之宮病院、兵庫医科大学病院、京都先端科学大学を経て、2024年4月より現職。臨床に注力する一方、県立広島大学大学院では口腔運動と発話の研究、大阪大学大学院では口腔運動と嚥下(飲み込み)の研究を行い、口腔運動のトレーニング方法の開発に取り組んでいる。
飲み込む機能が低下するのはなぜ?
食べ物や飲み物を飲み込むことを示す「嚥下(えんげ)」は、「舌」や「口唇(こうしん)」など、口やのどの様々な器官の動きによって行われています。脳梗塞による麻痺やがんの手術による器官切除、加齢による筋力低下などにより飲み込む機能が低下し、嚥下障害が生じます。
★実際に体験してみよう!
普段何気なく行っている舌や口唇の動きが制限された時、飲み込むことがどれくらい難しくなるか実際に体験してみましょう。
① 口唇を開けた状態で水を飲む
水を口に含み、口唇を開けた状態で固定したまま飲み込んでみましょう。口唇に麻痺がある方や高齢で口唇の動きが悪くなった方も同じように飲み込みにくくなります.
② 舌を動かさずに水を飲む
次は口の中で舌を動かさずに水を飲み込んでみましょう。①はクリアできた方も、これはかなり難易度が高いのではないでしょうか。舌がんや脳梗塞、パーキンソン病などで舌の動きが悪くなった方は、このような飲み込みにくさを抱えながら食事を行っています。
嚥下調整食って何?
食べ物の食べやすさは、主に「やわらかさ(おせんべいのように固いものは咀嚼しにくく飲み込みにくい)」「はりつきやすさ(海苔やワカメのようにはりつきやすいものは喉に詰まりやすい)」、「まとまり(ミンチ肉などまとまりがないものは飲み込む時にむせやすい)」、「水分の分離(ゼリーなど固形部と水分が分離しているものは飲み込む時にむせやすい)」などによって決まります。嚥下調整食はこれらの点を考慮してつくられた、咀嚼・嚥下能力に不安がある方向けの食事です。嚥下調整食は食べやすさによってレベル分けされており、対象者は医療機関で適切な咀嚼・嚥下能力の評価を受けることで、自分に合ったレベルの嚥下調整食を選べるようになります。嚥下調整食の分類には、病院で使われている学会分類2021や農林水産省が提案するスマイルケア食など様々な基準があり、例えば市販の嚥下調整食品において頻繁に適用されているユニバーサルデザインフード(UDF)では、咀嚼力に合わせて「容易にかめる」「歯ぐきでつぶせる」「舌でつぶせる」「かまなくてよい」の4つにレベル分けされています。

嚥下調整食を食べる患者さんの心情は?
嚥下調整食は食事の安全を守るために必要なものですが、対象者が好んで食べることは少なく、むしろ抵抗を感じている方が多いのが現状です。例えば嚥下調整食の味は開発が進むにつれて改善されてきていますが、飲み込みやすくするために食感や香りが損なわれることも多く、通常の食事と比較すると満足感は低くなります。また食事を複数人で楽しむ際、自分だけが嚥下調整食を食べることに疎外感や孤立感を感じる方もおられます。普段は嚥下調整食を摂取している方が、来客時に「自分だけ違うものを食べるのは失礼だ」と考え、無理して同じものを食べた結果、誤嚥を引き起こした事例もあります。
対象者と一緒に暮らす家族や食事指導をする医療者は、安全な方法で食事介助を行う、食べる順番を調整するなど、安全に飲み込めるように配慮するとともに、これまでの食事を食べることが出来ない心情を理解し、対象者の尊厳に配慮しなければなりません。

進化する嚥下調整食!
安全性を優先するあまり、見た目が損なわれるとされていた嚥下調整食ですが、近年では対象者の食べる喜びに配慮した商品が多数開発されています。
たとえば煮物やうどんなど料理の形は残しながらも、舌やスプーンで容易につぶせる柔らかさに加工した「あいーと」という商品があります。
酵素均浸法という方法を用いて食材の組織は壊さないまま加工しているため、普通の料理のような見た目を保ちつつ誰でも安全においしく食べることができます。例えば、普段の食事の一品を「あいーと」にしたり、お誕生日などのイベント食として提供したり、お正月など親族の集まるときに利用するなど、使い方次第で嚥下障害の方の「食事の楽しみ」が飛躍的に向上します。
また、流れるスピードが速く、誤嚥しやすい水やお茶などの水分はとろみをつけることで、誤嚥しにくい形態になります。最近では炭酸飲料に特化したとろみ調整食品「つるりんこシュワシュワ」が登場する等、安全性を確保しつつも喜びや楽しみを重視した商品が開発されるようになってきています。今後も対象者の心情に配慮した商品の開発が加速していくことが予想されます。

まとめ
種類豊富なおいしい商品が続々と登場している嚥下調整食ですが、まだまだ課題が残ります。今後、さらに嚥下調整食が発展していくためには、以下のような課題をクリアしていかなければなりません。
1.十分な栄養量が確保できる
2.日常的に購入可能な価格になる
3.食べる楽しみを感じることができる
上記の1~3のバランスが整うことで、嚥下障害を抱えた対象者が、日常的に「食べる喜び」を感じることが出来るようになります。食事を誰もが楽しめる社会にするために、これからの技術の進化に期待しましょう!
また今回嚥下調整食を紹介しましたが、どんな食べ物でも食べられる健康な口腔機能を維持することが最も理想的です。時間がある方は、下の記事を読んで嚥下筋を鍛えてみてくださいね。
「かみかみごっくん」その機能衰えていませんか?嚥下を知って鍛えよう!
この記事についてのご感想やご質問があれば、ぜひInstagramのコメント欄で教えてください!みなさんのコメントをお待ちしています✨
セラピア | Instagram