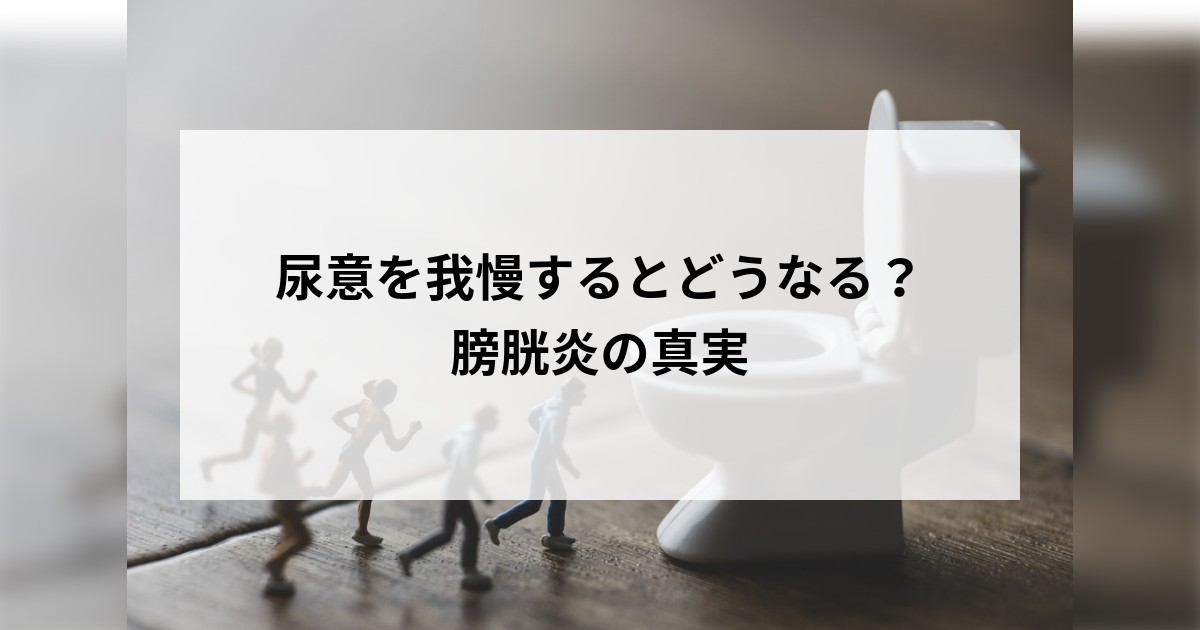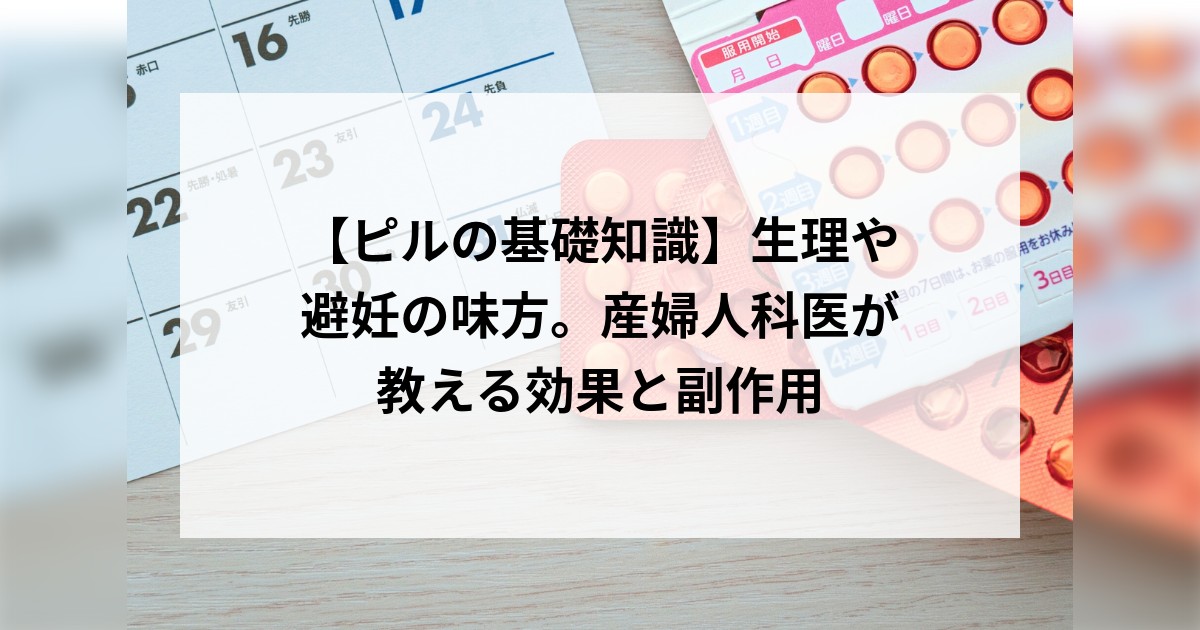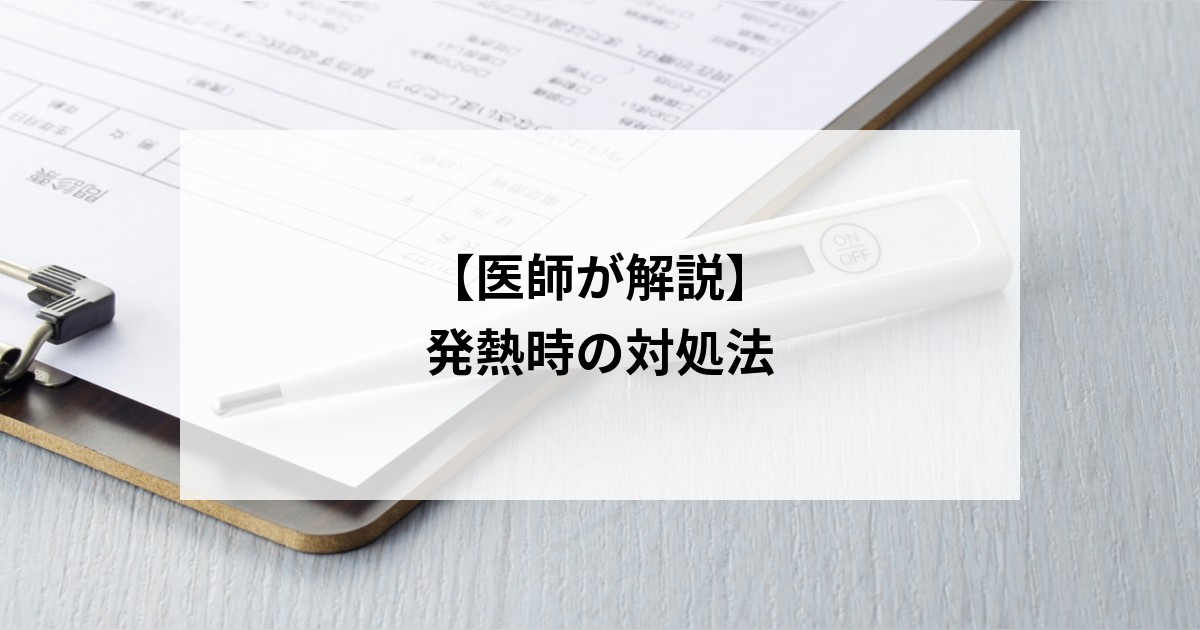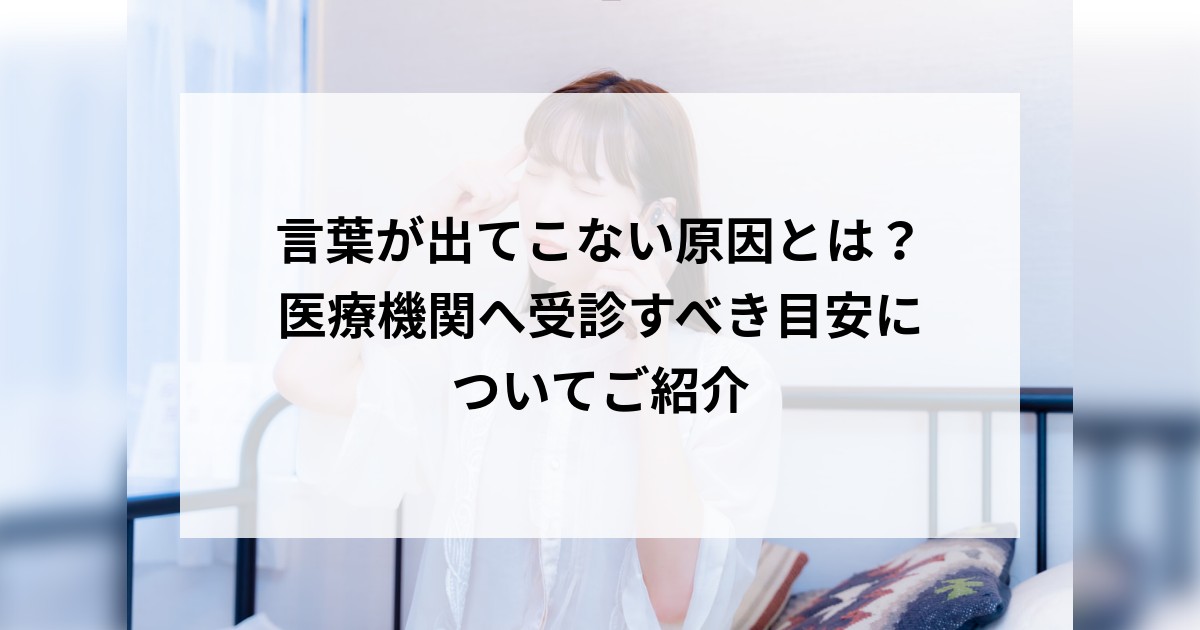184日にわたって行われていた「大阪・関西万博」が閉幕を迎え、万博ロスという言葉を耳にすることも。筆者は8月下旬に仕事で万博出展に携わる機会があったのですが、当日はお手洗いになかなか行けず…ということがありました。これ膀胱炎にならないかな?との疑問から、泌尿器科の先生に取材をしました。
今回、お話をお伺いした先生

公益財団法人日本生命済生会 日本生命病院 泌尿器科 副部長 湊のり子先生
2005年、神戸大学医学部卒業後、2年間の初期研修を経て2007年に大阪大学医学部泌尿器科に入局。JCHO大阪病院、大阪大学医学部附属病院、箕面市立病院、住友病院を経て 2017年より日本生命病院に入職。現在に至る。
膀胱炎とは。我慢するとダメなのか?
膀胱炎の定義は、膀胱に起きる細菌性の炎症のことで、尿路感染症※の1つ。尿路の基礎疾患(残尿が多い、尿路結石がある、膀胱癌があるなど)や、おむつの使用(蒸れや大便から)等により、尿道から膀胱に細菌が侵入することで罹患します。 よく言われる「尿意を我慢すると膀胱炎になる」は、実は関係ないそうです。若い女性の場合、性交渉後に発症するケース、ナプキンによる蒸れが原因となることもあります。さらにウォシュレットの使用が関与している場合があり、湊先生の患者さんにもウォシュレットの使用をやめると治った、という事例もあったそうです。(間質性膀胱炎など、細菌性の膀胱炎とは別の疾患も存在します。)
※尿路感染症:尿の通り道(尿路)で起こる感染症。尿路には膀胱や尿管、腎盂(じんう)等があり、場所により名称が異なります。

なりやすい人っているの?どんな症状があらわれる?
膀胱炎になりやすいのは、圧倒的に女性。肛門と尿道が近い位置にあることから、拭き方によっては細菌が移行して罹患します。一方、男性の尿路感染症の場合は膀胱炎よりも前立腺炎や尿道炎であるケースが多いです。膀胱炎の典型的な症状としては、
・頻尿、残尿感、尿意切迫感
・下腹部痛、排尿時痛
・尿が白く濁る(白血球が混ざる。状態によっては、薄黄色の膿のような尿になることも。)
・血尿(出ることもあるが、尿路結石やがん等の他疾患の可能性もあるので注意が必要)など
尿の色の変化には、自身で気が付かないことが多いです。また、膀胱炎では発熱は認められません。発熱があるときには腎臓や前立腺など、他の部位に感染を起こしている可能性が考えられます。
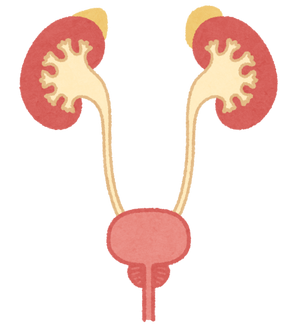
膀胱炎になったときの治療法
・漢方系の市販薬:抗菌作用は基本的にないものの、症状を抑える効果がある。
・水分摂取:しっかり水分をとることで、細菌の排出を助ける。
・抗生剤:必要に応じて使用します。軽症なら抗生剤なしで自然治癒することも。
膀胱炎が重症化して生命に関わることはありません。しかし細菌が膀胱から腎臓へ逆流し、急性腎盂腎炎(じんうじんえん)になる場合や、男性であれば細菌尿から急性細菌性前立腺炎や精巣上体炎になる場合もあるので注意が必要です。
通常 、膀胱炎では膀胱鏡検査は行いませんが、他疾患の鑑別目的などで尿の濁りの強い患者さんの膀胱をカメラで覗くと、膀胱内がスノードームのように見えることがあるそうです。そのような状態になっている場合、尿のにおいが強いのだとか。また、出血性膀胱炎では、血が固まり尿道が詰まってしまうことがあるため膀胱洗浄を実施し、古い血の塊を排出します。

スノードームのように見えるというのは、驚きと尿路感染症の怖さを感じます。(画像はイメージです)
受診のタイミング
上述のとおり、軽度であれば自然治癒することもあります。経過を見て10日前後症状が治まらない、繰り返し症状があらわれるといった場合には、医療機関を受診しましょう。膀胱炎だと思っていたら、尿路結石やがんが見つかるケースもあります。
また、検尿を採るときは出始め・出終わりは避けて中間尿をとりましょう。中間尿を採取することで、尿道口付近の(皮膚表面の)雑菌や、女性であればおりものの混入を減らすことができ、正しい診断ができます。これから尿検査を行うときには、意識しておきたいですね。
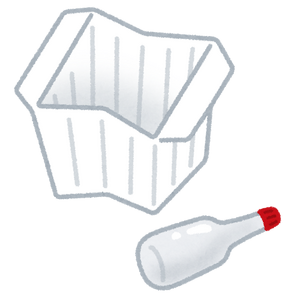
そのほか素朴な疑問をお聞きしました
水分は摂取すればするほどよいというのは?
過剰摂取は水中毒(電解質異常)の危険があり、よくないです。(筆者は1日5リットル程度飲みますが、これはやや飲みすぎとのこと。)
女性はどの診療科を受診したらよいですか?
泌尿器科で診療できます。コモンディジーズとして一般診療で扱われるため、内科・婦人科でも対応可能です。
とても尿がくさいときがあるのですが、これはどうしてですか?
尿の混濁が強いときには、強いにおいがする患者さんもおられます。しかし、尿のにおいは食事由来で日々変化します。特にアスパラガスやニンニクなどは強いにおいに繋がることがありますが、食べ物が原因であれば心配ありません。ただ、強いアンモニア臭や甘い匂いが続いた場合などは、病気が隠れている可能性もあるので内科受診をおすすめします。(たしかに!ニンニク入り旨辛ラーメンを食べるとそうなる気が…と筆者も身に覚えあり。)
湊先生にお伺いして「そうなのか!」と勉強になることが多くありました。日々の生活でのお手洗いの際、拭き方には気を付けて、よく水分摂取をして健やかな毎日を過ごしたいと感じました。
公益財団法人 日本生命済生会 日本生命病院

1924年7月、財団法人「日本生命済生会」設立。日本生命本館内に事務所を設置して診療を開始。1931年6月、名門緒方病院の土地・建物を継承し、大阪市西区新町に「日生病院」を開院(当初は24床で開始)。2018年4月30日、大阪市西区江之子島に新築移転。病院名称を「日生病院」から「日本生命病院」に変更し、現在に至る。
所在地|〒550-0006大阪市西区江之子島2丁目1番54号
病床数|一般350床
診療科|
循環器内科、消化器内科、内分泌・代謝内科、呼吸器・免疫内科、血液・化学療法内科、脳神経内科、腎臓内科、消化器外科、呼吸器外科、乳腺外科、心臓血管外科、産婦人科、小児科、神経科・精神科、脳神経外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉・頭頸部外科、形成再建外科、放射線診断・IVR科、放射線治療科、麻酔・緩和医療科、リハビリテーション科、救急総合診療科、検査診断科、病理診断科、予防診療科
診療センター|
救急総合診療センター、がん治療センター、女性骨盤底センター、糖尿病・内分泌センター、消化器内視鏡センター、血液浄化センター、脳機能センター、乾癬センター、ニッセイ予防医学センター
その他|
病院機能評価認定病院(3rdG:Ver.2.0)
ジャパンインターナショナルホスピタルズ(JIH)推奨病院
卒後臨床研修評価機構(JCEP)認定病院
人間ドック・健診施設機能評価認定病院(Ver.4.0)
DPC対象病院
大阪府がん診療拠点病院
地域医療支援病院
この記事についてのご感想やご質問があれば、ぜひInstagramのコメント欄で教えてください!みなさんのコメントをお待ちしています✨
セラピア | Instagram
【この記事を書いた人】
はくまい
美味しいごはん(とお酒)が大好き!ごはんのために働き、ごはんのために眠る!!今日もカロリーと幸せを噛みしめ、数字より気持ちで生きる30代おなご。