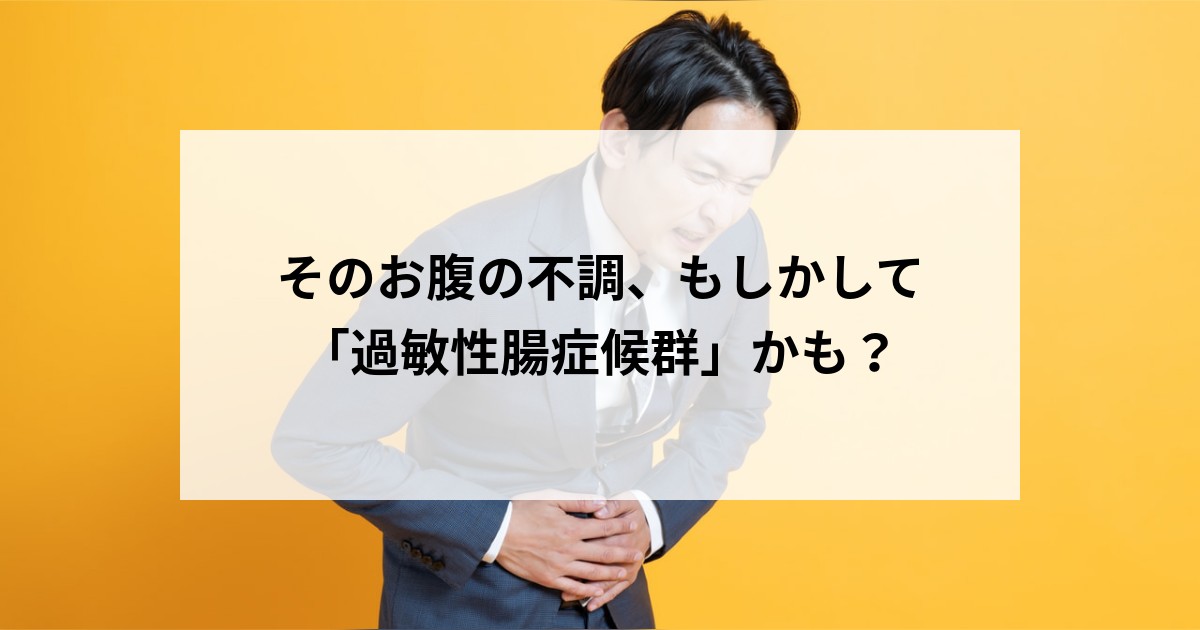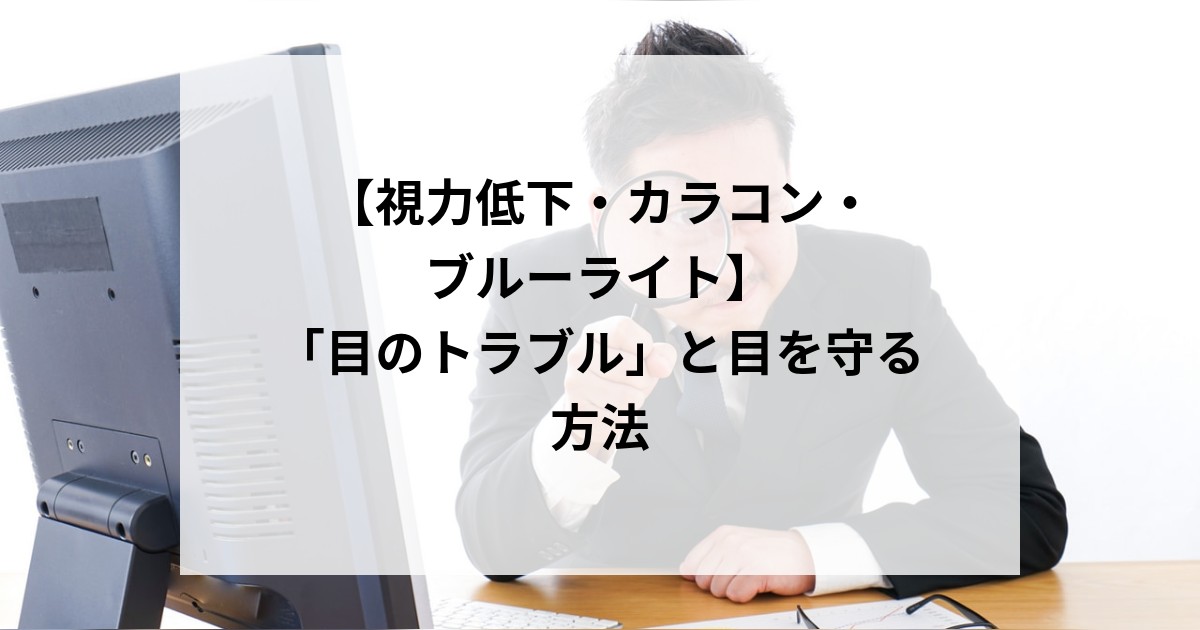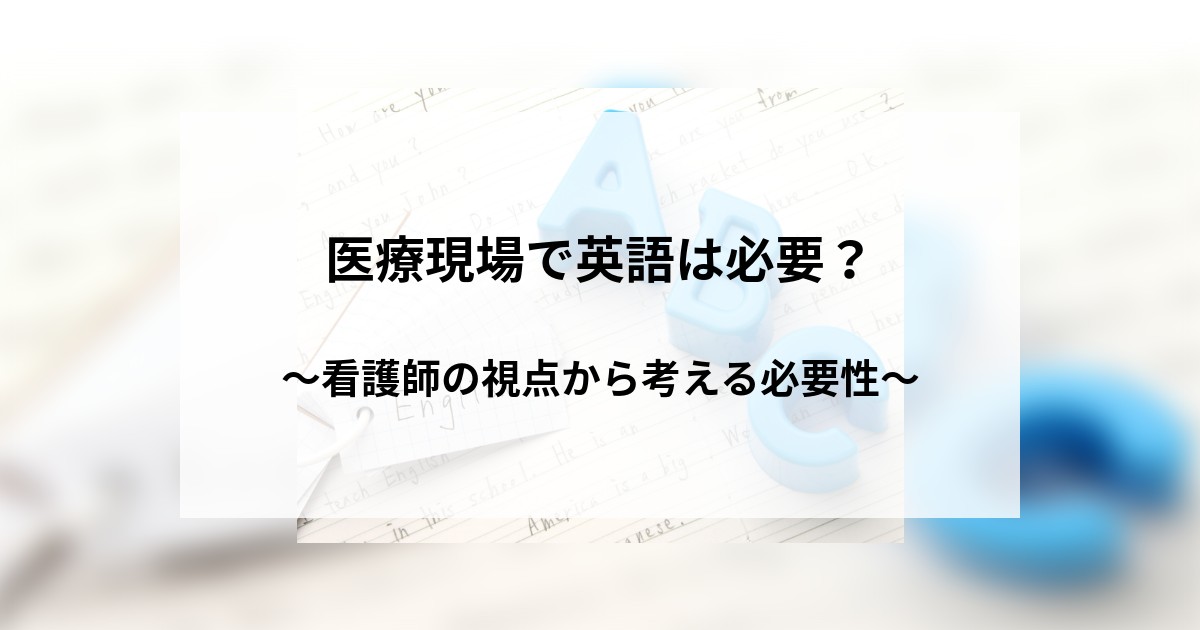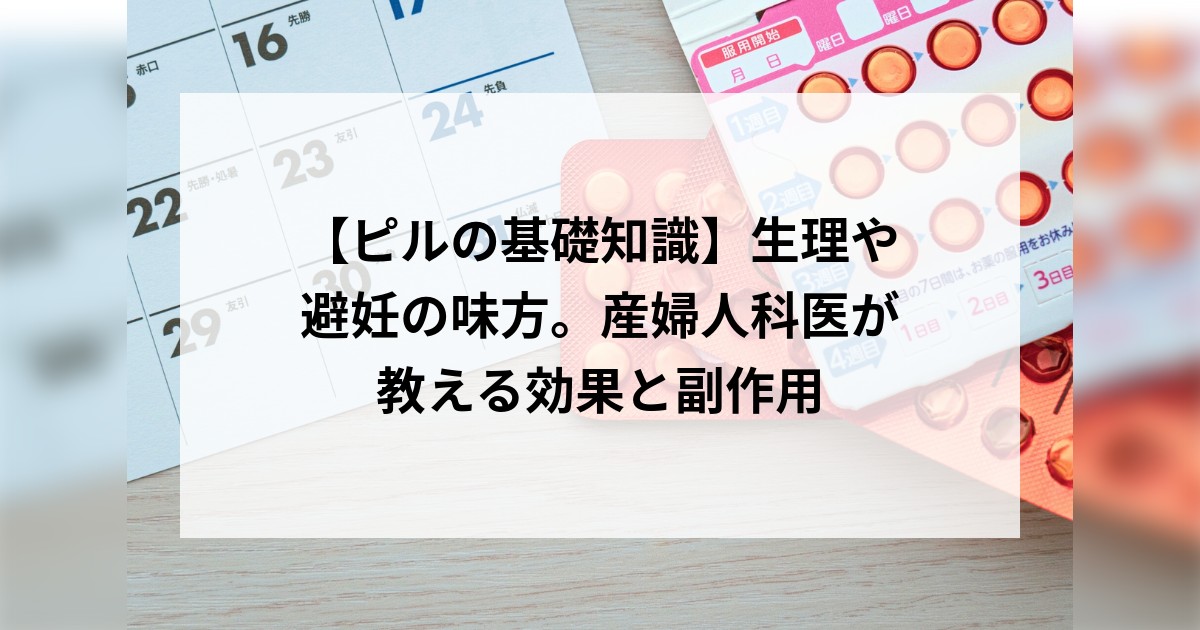「またお腹が痛くなったらどうしよう」
「あの駅のトイレの場所は…」
何を隠そう、通勤時の私自身です。いつもこんな不安から、通勤ルートを“トイレ基準”で考え、頭の片隅でトイレの場所を地図のように思い浮かべており、長年の悩みの一つでした(今でこそ記事のネタにできるようになりましたが…)。
そこで今回は、過敏性腸症候群(Irritable Bowel Syndrome:以下IBS)という病気をご紹介します。
私と同じように悩んでいる方にも知って安心してもらうため、中年筆者の頼れる味方、前川先生にお話を聞いてきました。
今回お話をお伺いした人

森ノ宮医療大学 医療技術学部 学部長(教授)・副学長/医師 前川 佳敬 先生
島根医科大学 医学部医学科卒業後、大阪大学大学院 医学系研究科生体制御医学専攻 博士課程修了(博士)。大阪大学医学部附属病院内科系研修医、桜橋渡部病院 循環器内科、大阪大学医学部附属病院 保健医療福祉ネットワーク部 副部長などを経て、2016年4月森ノ宮医療大学 保健医療学部(現:医療技術学部) 臨床検査学科 教授に就任。2022年より現職。
IBSの症状は人それぞれ
IBSは腸に明らかな病変がないにも関わらず、腹痛や便通の異常が慢性的に続く疾患です。
原因はまだ完全には解明されていませんが、細菌やウイルスによる感染性腸炎にかかった(腸の粘膜が弱くなり、腸内細菌も変化)後に 罹患しやすいことが知られています。
その症状は、便の形状と頻度から4つの型に分かれます。
便秘型:ストレスを感じると便秘がひどくなる(女性に多い傾向)
下痢型:緊張すると腹痛や下痢を生じる(男性に多い傾向)
混合型:下痢や便秘など、変動的な便通異常を起こす
分類不能型:いずれにも当てはまらない
と、症状は人それぞれで、検査しても明確な原因が見つからないことから、「気のせい」や「ストレスのせい」と片づけられやすいのが現状です。
ですが実は、日本人の約10人に1人がこの病気を抱えているといわれており、男性よりも女性に多く、思春期から壮年期まで幅広い年代で見られます。
 これだけ空いてたら最高…
これだけ空いてたら最高…
腸の中は“花畑”!? 腸内フローラって何?
腸内には、腸内環境に影響する腸内細菌が1,000種類・100兆個以上も存在し、その総重量はなんと1kg以上あるといわれています。
これらが種類ごとにまとまり、腸内に花畑のように広がっていることから「腸内フローラ」と呼ばれています。
ヒトの細胞は約37兆個といわれているため、腸内細菌の多さがよくわかりますね。
腸内細菌は大きく3種類に分類されます。
善玉菌:乳酸菌・ビフィズス菌など。悪玉菌の増殖や活動を抑制、免疫調整など。
悪玉菌:大腸菌(有毒株)・ウェルシュ菌など。有害物質をつくり出すことなど。
日和見菌:善玉菌、悪玉菌のうち、優勢な菌と同じ働きをするなど。
まだまだ研究途上の分野だそうですが、理想的なバランスは「善玉菌2:悪玉菌1:日和見菌7」。
近年の研究では、このバランスが崩れるとIBSだけでなく、炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)※、大腸がん、生活習慣病、アレルギー疾患、さまざまな感染症、認知症、うつ病など、幅広い疾患の発症リスクを上げることがわかってきています。
バランスを保つためには、規則正しい生活を送り、栄養バランスがとれた食事を摂ることが重要と考えられています。
※日本では難病法により指定難病に定められており、医療費助成の対象になっています
ちなみに、ミルク(乳糖)を飲むとおなかにガスがたまる、下痢をするなどの乳糖不耐症は、この腸内細菌が関係しています。
赤ちゃんの時には消化できていたミルクが成長とともに分解できなくなるのは、小腸で乳糖を分解する酵素「ラクターゼ」の分泌が年齢とともに減少するため。
これは成長に伴い、母乳以外の食物から栄養摂取できるようになることで酵素が不要になるから、とされています。
実は「口の中」も関係している
意外に思われるかもしれませんが、歯周病菌など口腔内の細菌が腸に移動し、腸内環境を悪化させることがあります。
そのため健全な口腔細菌叢(こうくうさいきんそう)を回復し、それを維持することは全身の健康にとても重要です。
「腸活」といえば食事ばかりが注目されがちですが、口腔ケアも立派な腸活の一つといえますね。
【関連記事】歯の土台がなくなる…歯周病をコントロールせよ!
「脳」と「腸」の会話がズレると、腸が暴走
最近では「脳腸相関(のうちょうそうかん)」という考え方が注目されています。
脳は、自律神経系・ホルモン・サイトカイン※ などを介して腸と密接に関連し、腸運動と変化を感じとる知覚を調整しています。
私たちがストレスを感じると双方の信号が強くなり、 “脳と腸の会話”がうまくいかなくなることで、腸の運動異常や知覚過敏状態を引き起こし、便通の乱れや腹痛として現れると考えられています。
※細胞同士の情報伝達作用を持つ物質

余談ですが、前川先生も高校生の時、特にテスト期間などはIBSの症状に悩まされていたそう。
タイムマシンがあったらあの頃の自分に、あまり心配せず生活習慣を改めるように優しく伝えたいとおっしゃっていました。
IBSは“体質”ではなく“治療できる病気”
IBSは、潰瘍性大腸炎やクローン病、大腸がんなど、似た症状を持つ病気が隠れている可能性もあるため、自己判断は禁物。
生活の質を大きく下げてしまう可能性のある疾患でもあるので、「これくらいは…」と思わず、気になる方は一度、医師に相談してみましょう。
腸の動きを調整する薬物療法をはじめ、食事療法・運動療法・心理療法などさまざまなアプローチがあるため、あなたに合った治療を受けることができるはずです。
まとめ:腸はあなたの体調と心のバロメーター
IBSは特別な病気ではなく、多くの方が悩んでいます。
安心して毎日を過ごすため、まずはあなたの腸が出すサインに耳を傾け、医師へ相談してみましょう。
“トイレの場所を調べる”以外にも、きっといい治療法が見つかるはずです。
なお今後は、今回ご紹介した腸内フローラを整えるための方法や、腸が元気になることで得られる意外なメリット、IBSに関する最新のトピックスなどをご紹介する予定です。
お楽しみにお待ちください。
トイレを見つけるコツ、こんな対策をしているよ!など、みなさんのIBSに関するエピソードがあればぜひ、Instagramのコメント欄で教えてください!たくさんのコメントをお待ちしています✨
セラピア | Instagram
【この記事を書いた人】
カツオ
三度の飯より釣りが好き。三度の飯は麺が好き。な元サッカー審判員(ギリギリ30代のアラフォー男)