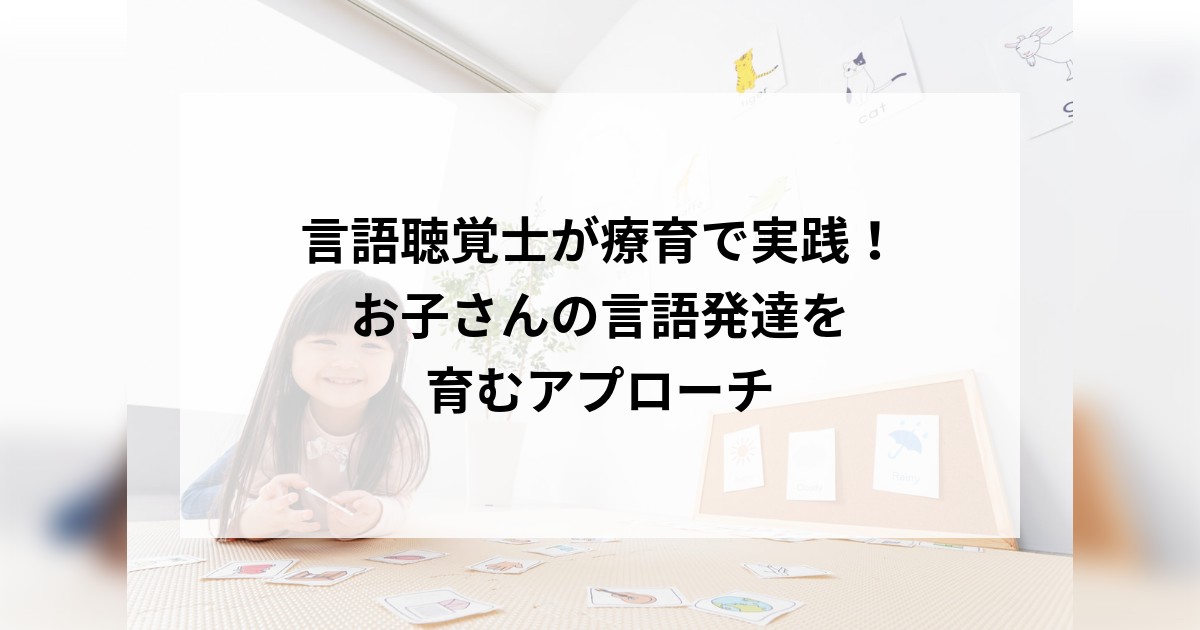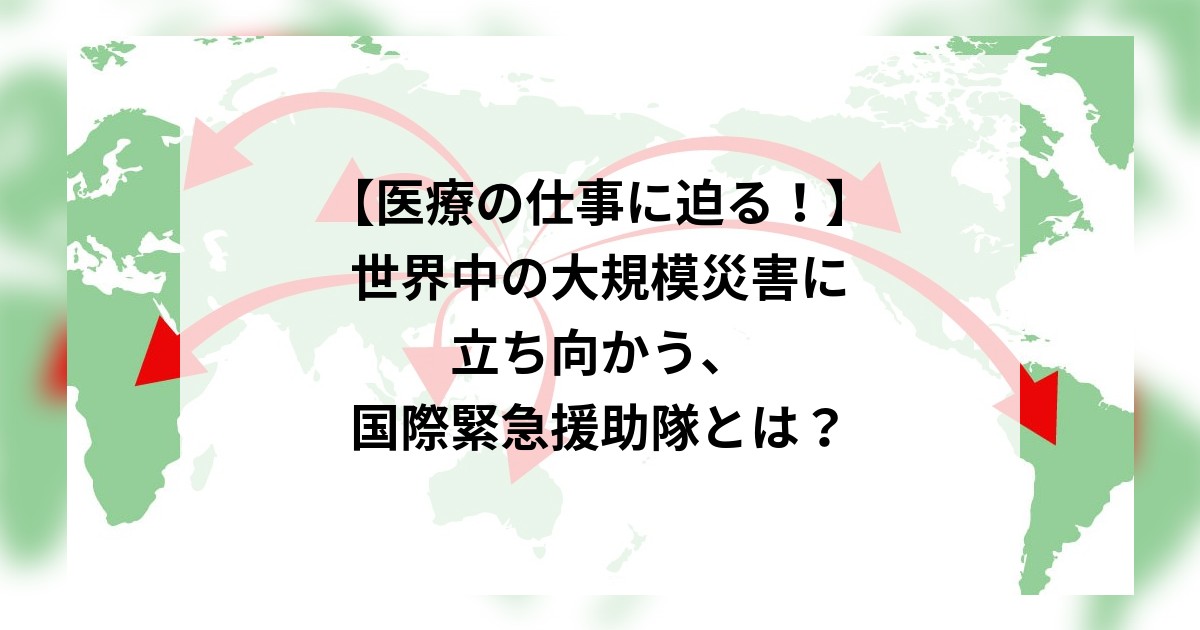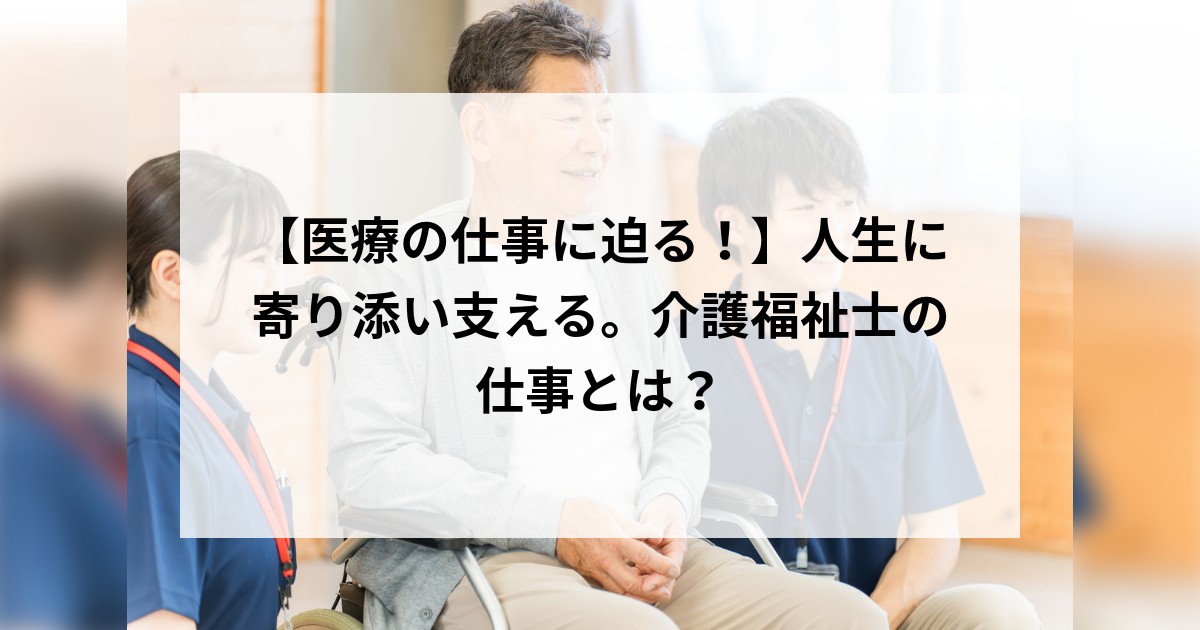お子さんを育てる保護者の中には、言語面での発達について気にされている方も多いのではないでしょうか。今回小児における言語発達の専門家である言語聴覚士の鮎澤先生に、言語発達に必要な各要素へのアプローチ、保護者からお子さんにしてしまいがちな言語面でのNG行動について伺いました!
今回お話をお聞きした人
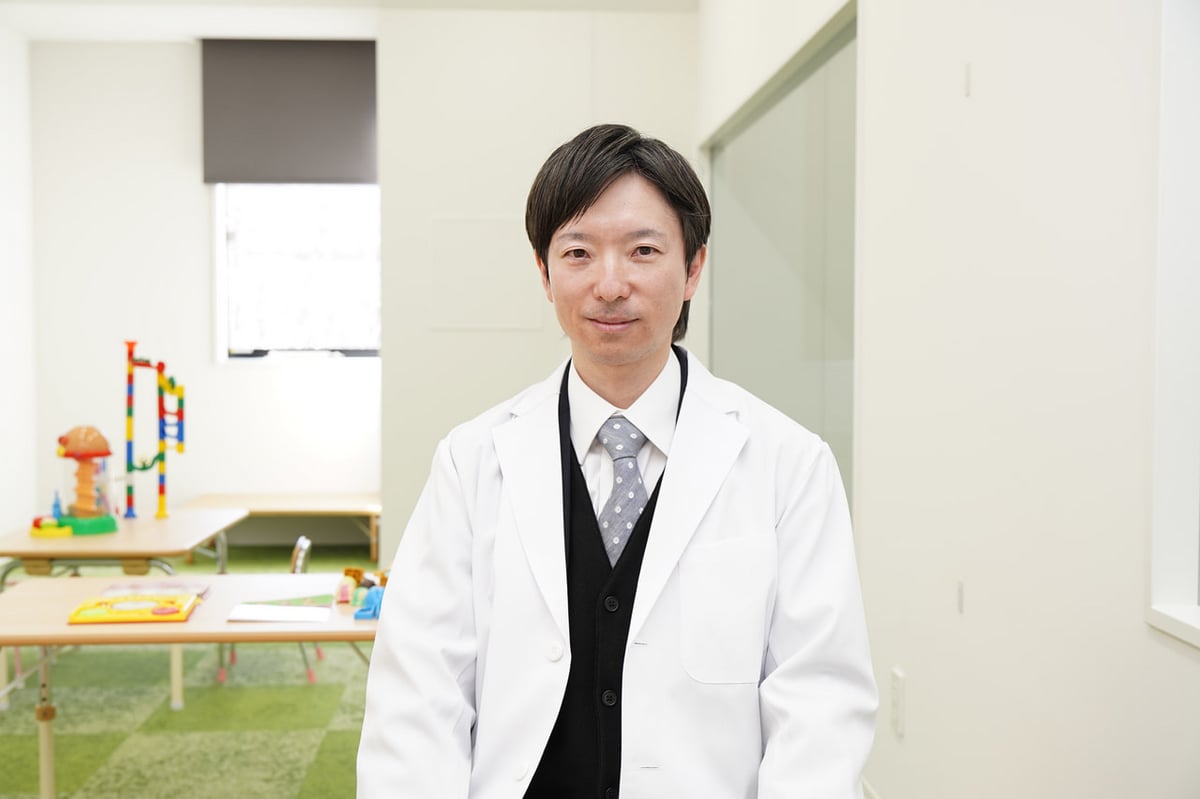
森ノ宮医療大学 総合リハビリテーション学部 言語聴覚学科
講師/言語聴覚士 鮎澤 俊平先生
専門里親として入れ替わりで数十人の里子を受け入れていた実親の影響で、日本と外国の社会的集団養護のスタイルの違いに興味を持ち、セントラル・ワシントン大学で家族学(Family Studies)を学ぶ。大学院修士課程在学中にコロラド州デンバーにて修復的愛着療法を実践する3名の心理士の下インターンに参加し、帰国後は埼玉県初の児童心理治療施設の立ち上げに従事。聴覚障害を持つ児童とのかかわりをきっかけに言語聴覚士を志し、大阪保健医療大学言語聴覚専攻科を卒業。病院や民間の療育施設で勤務した後、2024年4月より現職。
言語発達に必要な4要素を育むためのアプローチとは?
療育(発達支援) を利用する子どもの言語発達には生物学的基礎・社会的基礎・認知的基礎を築くことが不可欠です。そのために言語聴覚士は、語彙理解、模倣、呼気・発声、環境へのアプローチを大切にしています。
・語彙理解
お子さんが言葉を正しい意味で理解しているかどうか評価するのは、案外難しいものです。例えば、夕食時に「ごはんできたよー」と声かけをするとお子さんが席につくことができるという理由で、言葉の意味を理解していると判断するのは早計です。なぜなら言葉ではなく、机の上に食事がある状況で声をかけられる習慣に反応している可能性があるためです。鮎澤先生は、本当に言葉の意味を理解しているのか確認するために、いつもの声かけを普段と違う場所でしてみてはどうかと保護者に助言をするそうです。 指示に応じられる子どもには、絵本を見せながら「〇〇はどれ?」というように指差しを促すなどの方法があります。
・模倣
子どもは大人の真似をすることで行動と言葉を結び付けるため、模倣は言語発達にも社会性の発達にも必要不可欠です。模倣が遅れて いるお子さんへのアプローチとしては、子どもと遊びながら、反対に保護者がお子さんの行動を適宜真似してみるのが効果的です。自分が真似されているのに気づくと、自発的に真似をしてくれることがあります。
・呼気・発声
言葉を話すためには、正しい呼気・発声方法を修得する必要があります。子どもはしゃぼん玉や吹き駒など、息を吹きかけて楽しむ遊びを通じて、意図的に呼気をコントロールする力や発声する力を身につけることができます。
・環境
鮎澤先生が療育で初めに伝えているのは、「規則正しい生活を送ることの大切さ」。規則正しい生活を送ることで日々の行動がルーティン化し、お子さんが繰り返し行動と言葉を結び付けて学ぶことができるからだそう。不規則な生活を送るとこの繰り返しがなくなるため、言語発達のための学びの機会が減ってしまうそうです。

やってしまいがちだけど...お子さんの言語発達を妨げるNG行動
保護者がやってしまっていることが、もしかしたらお子さんの言葉の発達を妨げているかもしれません。そんなついついやってしまいがちなNG行動2選をご紹介します!
・赤ちゃん語で話しかける
「靴」を“くちゅ”、「チョコ」を“こちょ”など、お子さんが言葉の発音を修得するタイミングでしてしまう言い間違いは、とても愛くるしいものです。しかし、かわいいからといってそれを大人が真似して「くちゅ履こうね」などと話しかけるのはNG!お子さんの発音修得を助けるために、正しい発音を伝えていく必要があります。
ただし、「ごはん」を“マンマ”、「車」を“ブーブー”というように、言葉を話す前のお子さんに対してより発音しやすい幼児語を使うことは、反対にお子さんの語彙力増加を助けることが分かっています。言葉を修得する前の助走として、積極的に使っていきましょう。
・お子さんの要求に先回りして応える
言葉をうまく使えないお子さんが何かを訴えようとしている時、よかれと思って先回りして要求に応えていませんか?これも実は言語発達において好ましくない行動です。
赤ちゃんは泣くことで要求を発信しますが、次第に指さしを覚え、何を要求しているのか大人に伝えようとします。指さしで伝えられる内容には限りがあるため、癇癪を起こすこともありますが、徐々に言葉を修得していきます。しかし、大人がお子さんの発信を待たずに要求を満たしている場合はどうでしょう。お子さんは自分からアクションを起こさなくてもやってもらえる環境に慣れてしまい、言葉を使わなくなってしまいます。
周囲の状況やお子さんを育てる保護者の都合によっては難しいこともあるかと思いますが、できる限りお子さんからの発信を待ち、発信がない時には促してみるとよいでしょう。

まとめ
近年は保護者の中でも早期療育の重要性や発達障害への理解が進んでいるため、受診のハードルも低くなっています。お子さんの言語面での発達が気になったら、かかりつけの小児科に相談してみましょう。
また、療育を受けるためには市区町村の役所で受給者証を発行してもらう必要があります。療育を実施している児童発達支援センター や放課後等デイサービスをいきなり訪ねても、すぐに受けられるわけではないので要注意です。
子育てでは不安なこと・分からないこともつきものですが、専門家の助けも借りながら、お子さんの成長を見守っていきましょう。
この記事についてのご感想やご質問があれば、ぜひInstagramのコメント欄で教えてください!みなさんのコメントをお待ちしています✨
セラピア | Instagram